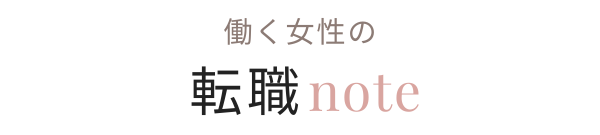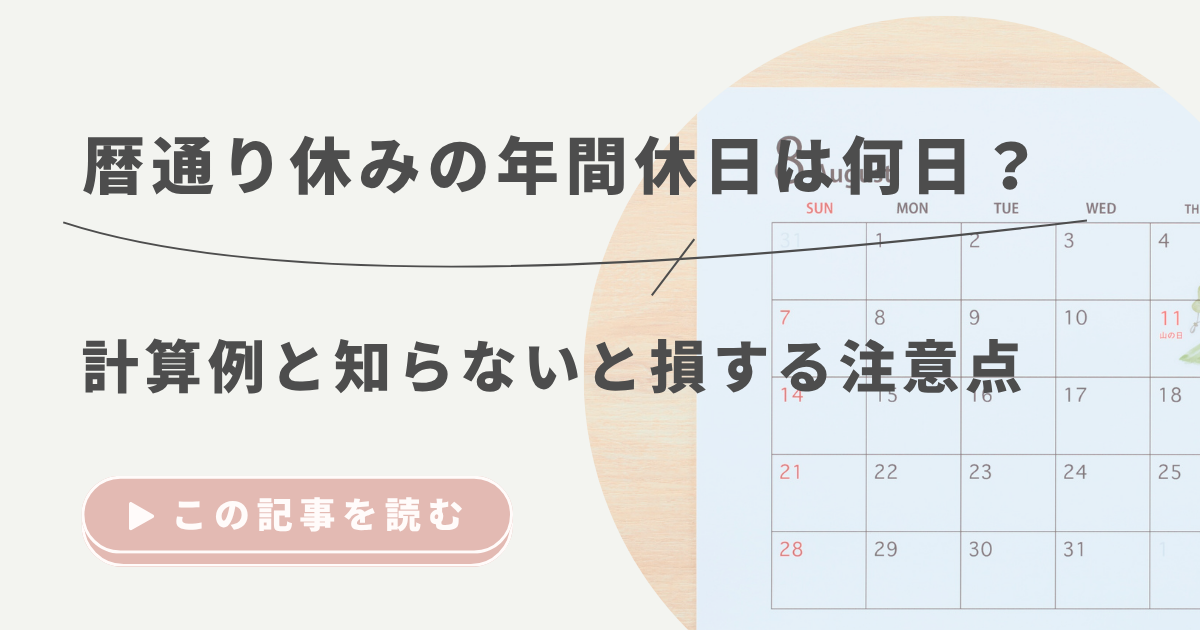・暦通りの年間休日は土日祝が基本で、おおよそ120日が目安
・年末年始やお盆などの長期休暇は、企業ごとに差がある
・暦通りの休み=ホワイト企業とは限らず、実態の確認が必要
転職サイトや求人票で「年間休日:暦通り」との表記をよく見かけるのではないでしょうか。一般的には土日祝日が休みのイメージですが、実際には企業によって長期休暇の扱いが異なります。
「暦通りの休みって実際に何日休めるの?」
「年末年始やお盆は必ず休めるの?」
「暦通り=ホワイト企業と言えるの?」
「あえて日数をわかりづらくしている?」
表現がわかりづらく明確な数字が記載されていないと、実際に何日休めるのか気になりますよね。
この記事では、2024年〜2026年の暦通り年間休日の具体例や、年間休日に含まれる日・含まれない日、ホワイト企業の目安まで解説します。
最後まで読めば、年間休日を正しく把握し、あなたに合った転職先を見極める判断力が身につきます。
本記事のライター:伊藤えま
採用・人事歴10年以上。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)取得済み。採用統括責任者として現場で得てきたリアルな知見を、発信している。
年間休日「暦通り」とは?基本の考え方

転職活動をしていると「年間休日:暦通り」との表記を目にすることがあるでしょう。一般的には「土日と祝日は休み」の意味で使われますが、細かな運用は会社ごとに異なります。ここでは、年間休日の定義と基本を確認しておきましょう。
年間休日の定義と労働基準法の最低基準
年間休日とは、企業があらかじめ定めている「1年間で社員が休める日数」のことです。労働基準法では、週に1日または4週間に4日以上の休日を与えることが最低ラインとされています。
出典:厚生労働省ホームページ
たとえば、1日8時間労働を前提に計算すると、年間休日の下限はおよそ105日になります。
とはいえ、実際は土日祝日を休日とするケースが多いため、法定最低基準を大きく上回るのが一般的です。年間休日が120日以上あれば、土日祝に加えて年末年始やお盆の長期休暇も取れる会社が多いでしょう。
「暦通りの休み」とは
「暦通りの休み」とは、カレンダーにある土日祝日をすべて休日とする働き方を指します。追加の休日を設けられるわけではないため、特別休暇は少ない一方で、予定が立てやすく、プライベートの計画がしやすいのが特徴です。そのため、プライベートを重視する人に向いています。
しかしながら、暦通り休みを採用している企業でもルールに違いがあります。たとえば、年末年始を「5〜6日の連休」としている企業もあれば、「1月1日だけ休み」とする企業もあります。年末年始の間で、祝日となっているのは1月1日のみです。暦通りといっても、長期休暇の取り扱いは企業によって差が出やすいのです。
求人票で「暦通り」と記載されていても、実際に年間休日が年日あるのかを確認することが大切です。
暦通りとカレンダー通りとの違い
求人票では「暦通り」や「カレンダー通り」という言葉が使われます。多くの場合、同じ意味ですが、厳密には以下のような違いがあります。
「カレンダー通り」と書かれている場合は、会社ごとのルールで休日が決められている可能性があります。休日が少ないことを隠す目的で、企業側があえて説明しないこともあるため「暦通りとの認識でよろしいでしょうか」と確認のために尋ねても問題ありません。
求人を見るときは「具体的な日数」や「完全週休2日制」といった表記を確認すると確実です。
暦通りだと年間休日は何日?具体例と計算方法
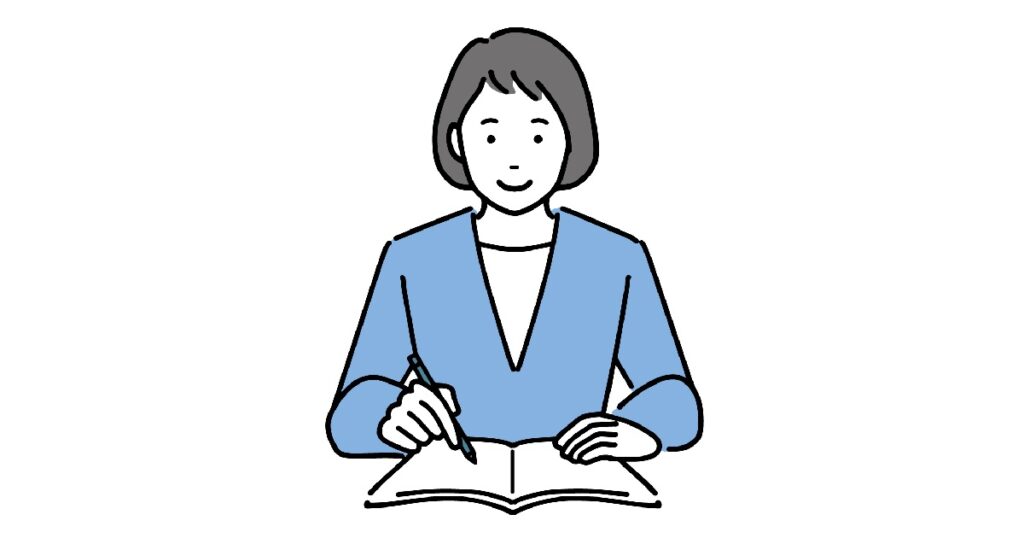
「暦通り休み」と聞いたときに気になるのは、1年間で実際にどれくらい休めるのかという点です。土日と祝日を単純に足し合わせると目安が見えてきます。ここでは具体的な計算方法と2024年〜2026年の例を確認しましょう。
1年間の土日の数・祝日日数をもとに計算
1年間には約52週あるため、土曜日と日曜日をすべて休みにすると104日前後になります。これに加えて、日本では16日前後の祝日があるため、合計するとおよそ120日前後が「暦通り休み」の目安です。
ただし、祝日が日曜と重なった場合は翌日が振替休日となるため、その年ごとに若干の増減があります。
2024年・2025年・2026年の暦通り年間休日
実際のカレンダーを元に「土日+祝日・振替休日」を数えると、次のとおりです。
- 2024年:118日
- 2025年:119日
- 2026年:121日
年によって118日〜121日と休日に違いがあります。求人票で「年間休日120日程度」と表記されている場合は、この数字を参考に比較すると良いでしょう。
年間休日に含まれる休日と含まれない休日
「年間休日」は、あらかじめ会社が全社員に一律で与える休日を指します。有給休暇や特別休暇とは別物である点に注意が必要です。
年間休日が120日とあっても、そのほかに有給や特別休暇を取得できれば、実際の休暇日数はさらに多くなります。たとえば、有給を10日消化した場合は、年間休日とあわせて130日の休暇が取得できるため、プライベート時間も十分確保できるでしょう。
年間休日の日数以外にも着目して、求人をチェックしましょう。
日本企業の年間休日の平均とホワイト企業の目安

年間休日の数は、働きやすさやホワイト企業かを判断するうえで、重要な指標のひとつです。ここでは平均値と目安を確認しましょう。
厚労省統計に基づく平均年間休日
厚生労働省「就労条件総合調査」によると、令和5年における年間休日の平均は112.1日でした。規模別に見ると次のようになります。
- 1,000人以上の企業:117.1日
- 300~999人:115.9日
- 100~299人:113.6日
- 30~ 99人:111.0日
出典:厚生労働省ホームページ
大企業ほど休日が多い傾向があることがわかり、休日制度も含めた福利厚生が整っている企業が多く見られます。平均値を把握しておけば、求人票に書かれた休日数が「多いのか少ないのか」をデータを元に判断できます。
ホワイト企業の目安は120日以上
一般的に「ホワイト企業」とされる目安は120日以上です。さらに年間125日を超える企業では、土日祝に加えて年末年始や夏季休暇も十分に取れるケースが多くなります。
大手メーカーや外資系企業では、独自の休暇制度を設け、130日近くになることも珍しくありません。さらに、有給を取得すれば150日前後の休日になることもあります。これは、年間で約40%が休みになる計算となり、充実したワークライフバランスを実現できます。
転職先を検討するときは「120日以上かどうか」をひとつの基準にし、自分のライフスタイルに合った休日日数を見極めるのがおすすめです。
年間休日が少ない職場のデメリット
休日が少ない企業では、心身の疲労が蓄積しやすく、ワークライフバランスの維持が難しくなります。その結果、離職率が高まり、採用が進まず残された社員の負担が増える「悪循環」に陥ることもあります。従業員満足度が低くなる傾向にあり、業務過多が加速する可能性があります。
仕事に求める価値観が違うため、休日数と給与に期待する理想的なバランスは、個人によって異なるものです。「年間休日105日」や「年間休日110日」と書かれた求人票に出会ったら、その休日日数に見合った給与や待遇になっているかを慎重に判断しましょう。
年間休日が多い傾向にある業界
年間休日が比較的多い業界には以下のような特徴があります。
- 金融業界(銀行・証券など):土日祝+年末年始休暇が基本
- 公務員:カレンダー通りに加え、まとまった長期休暇あり
- 大手メーカー:独自の休日を設け、125日以上のケースも多い
- IT・通信業界:フレックスや完全週休2日制の導入が進んでいる
- インフラ(電気・ガス・水道):大企業が多く、休日制度が整っている
一方、サービス業や小売業は休日が少なめで、暦通りに休めないことが多いのが現状です。業界ごとの傾向を理解しておくと、応募先を選ぶ際に役立ちます。
年間休日と法律の関係|義務化の誤解に注意

インターネットやSNSで「年間休日120日が法律で義務化される」といった情報が出回ることがありますが、現時点でそのような法律は存在せず誤解です。労働基準法が定めているのは「週1日以上の休日」と「年間5日以上の有給休暇の取得」であり、それをクリアすれば違法にはなりません。
年間120日以上は、休暇が多く好待遇な求人として、あくまでひとつの目安です。週2日の休日に加えて祝日で120日程度の休日となります。
誤った情報に惑わされず、求人票に記載された数字を正しく読み取りましょう。
暦通り休みは本当にホワイト?転職時に確認したい3つのポイント

暦通りの休日が設定されていても、実際は「休日出勤が多い」「有給が取りづらい」といったケースもあります。ここでは、働きやすい求人を見極めるポイントを解説します。
実際の休日数と有給取得率をセットで確認
転職活動では年間休日数だけでなく、有給取得率もあわせて確認しましょう。暦通り休みの企業であっても、有給が取りづらければ実質的な休みは減り、心身を休めてリフレッシュする機会を失います。
年間休日が120日あっても、有給取得率が20%しかなければ、結果的に休める日数は少なくなります。取得しやすい環境が整っていない場合、周りに遠慮して、義務化されている5日しか取得できない場合もあるでしょう。政府の目標として、2028年までに有給の取得率を70%とすることが掲げられています。
取得率を確認する方法は以下のようなものがあります。
- 企業のホームページや採用情報ページ
- 転職サイト
- 口コミサイト
客観的な情報を事前に確認すると、働きやすい企業に出会える可能性が高まります。
お盆休み・年末年始の実態や休日出勤の有無
お盆休みや年末年始など長期休暇や、休日出勤の有無もチェックしましょう。暦通り休みの会社でも、年末年始やお盆休みがどの程度休めるかは企業により差があります。
大手メーカーは「9連休」といった長期休みを設けることもありますが、中小企業では「12月30日〜1月3日の5連休」といったケースも珍しくありません。また、繁忙期に休日出勤が発生する企業では、振替休日が希望通りに適切に取れるかもポイントです。
実態を確認するためには、面接での質問や口コミサイトの情報が役立ちます。
求人票・口コミ・転職エージェントで確認すべき情報
求人票には最低限の情報しか記載されていないことも多く、実際の働きやすさを把握するためには複数の情報源を組み合わせての確認が有効です。特に、口コミサイトや掲示板では実際に働いた社員の声が見られるため、求人票だけでは分からない実態が把握できます。ただし、口コミは個人の体験に基づくため、偏りがある可能性は考慮しておきましょう。
具体的には以下のような手段で確認しましょう。
- 求人票で「週休2日制」「完全週休2日制」かを確認
- 口コミサイトで有給の取りやすさを調べる
- 転職エージェントに非公開情報や実際の休暇運用について質問する
理想的なのは、複数の情報源を照らし合わせることです。求人票だけではみえない、実態に近い労働環境を把握できます。
暦通りの年間休日のよくある質問や疑問
暦通りの年間休日についてよくある質問や疑問をまとめました。
- 暦通りだと年間休日は何日?
-
暦通りの休みは104日+祝日数(16日程度)=120日前後が目安です。ただし、祝日の並びや振替休日の有無によって前後します。
- 暦通りの年間休日は2025年の場合、何日?
-
暦通りの年間休日は2025年の場合、土日104日+祝日・振替休日15日=119日です。
まとめ|暦通りの年間休日を基準に転職活動を進めよう
この記事では、暦通りとした年間休日について解説しました。
暦通りの年間休日は、120日程度が目安です。これは、日本企業の平均年間休日である112.1日と比べると、多い水準といえます。ただし「暦通り=ホワイト企業」というわけではなく、有給取得率や休日出勤の有無を確認することが不可欠です。
あなたのライフスタイルに合った年間休日の多い求人を探すなら転職エージェントに相談してみましょう。