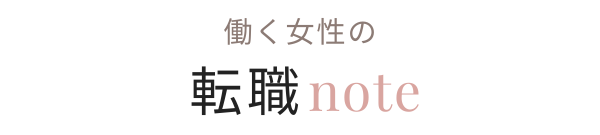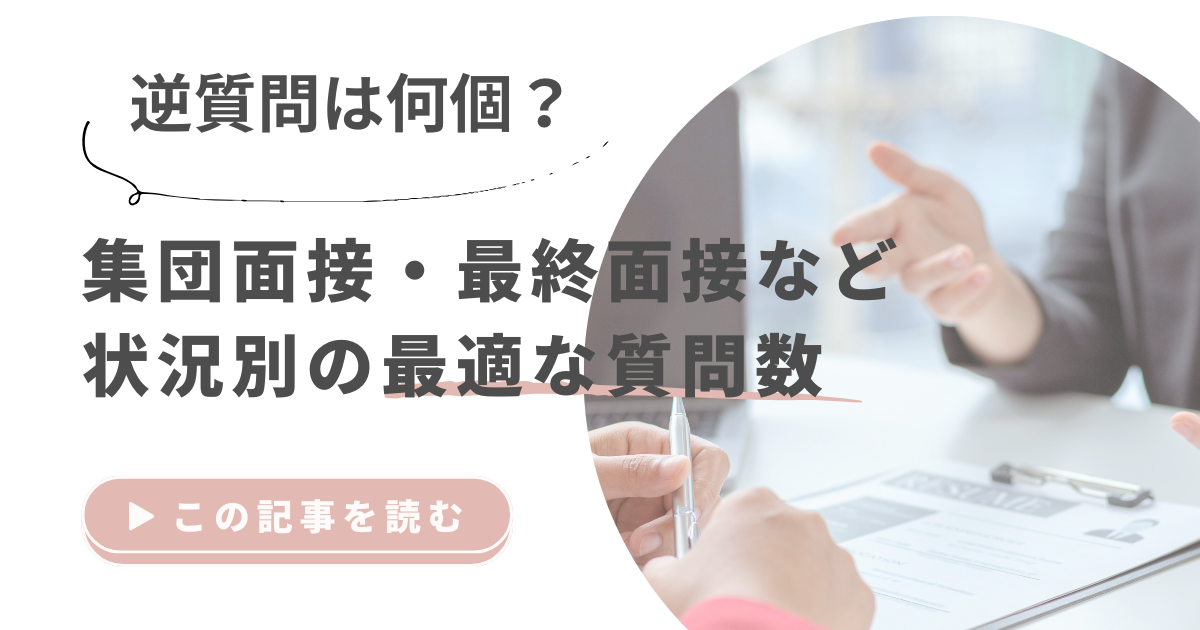- 逆質問は何個したらいい?面接の段階・時間別の目安
- 逆質問は何個用意しておくべき?
- 逆質問を考えるときの5つのポイント
- 逆質問をするときの3つの注意点
- 面接での逆質問の終わり方と印象を良くする締めくくり例
逆質問とは、面接の最後に面接官から「何か最後に質問はありますか?」と質問されることです。面接では基本的に企業側からの質問に答えるもので、応募者側から質問するのは「逆質問」と呼ばれます。

面接の逆質問って何個までしていいの?



逆質問は何個くらい準備しておけばいいのかわからない……
逆質問についてこんな不安を感じる人は多いです。結論から言うと、逆質問は1回の面接で2〜3個を目安に、段階や時間に応じて調整するのがポイントです。
この記事では、逆質問をする数や用意しておくべき数、印象を良くする終わり方についてわかりやすく解説します。
事前に準備する逆質問の数がわかり、面接で慌てることもなくなります。


- 採用・人事歴10年以上
- 中途採用で900名以上を選考
- 採用統括責任者として書類選考・面接・採否の決定を担当
- 人事評価基準の策定・人事考課にも従事
- 社員のキャリア相談を多数経験
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)
逆質問は何個したらいい?面接の段階・時間別の目安


逆質問の適切な数は目安として2〜3個です。ただし、面接段階や時間によって個数を変えるのがポイントです。
| 適切な数 | |
|---|---|
| 一次面接・集団面接 | 1個〜3個 |
| 二次面接 | 2個〜4個 |
| 最終面接 | 1〜2個 |
| 面接時間が短い場合(30分以下) | 1〜2個 |
| 面接時間が長い場合(1時間以上) | 3〜5個 |
一次面接・集団面接の逆質問
一次面接や集団面接では1個〜3個の質問をしましょう。基本的な能力やビジネスマナー、志望度を確認する場面なので多すぎない方がベターです。
業務内容や社風、求められるスキル感などの具体的な質問がよいでしょう。
二次面接の逆質問
二次面接では2個〜4個の質問が適切です。
一次と比較してより深い個人の価値観や能力、入社後のポテンシャルが見られています。一次の履歴は残してあることが多いので、同じ質問は繰り返さない方が無難です。仕事内容や配属部署の深堀り、評価制度の運用方法についての質問がおすすめです。
最終面接の逆質問
最終面接では1〜2個の質問にとどめておきましょう。
経営陣や役員との面接となるケースが多く、最終面接は時間が短めです。自分のキャリアプランや企業への貢献意欲が伝わる質問が、経営層にとっては好印象になります。
>> 【保存版】最終面接で落ちる人の特徴|転職で失敗しないコツ
>> 転職の最終面接で聞かれること・答え方|落ちない人が意識する5つのコツ
面接時間が短い場合(30分以下)の逆質問
面接時間にあわせて質問の数を調整するのも大切です。面接時間が短い場合には1〜2個の質問としましょう。面接時間が短いため、逆質問の時間があまりありません。
わかりやすく志望度がアピールできる質問がよいでしょう。
面接時間が長い場合(1時間以上)の逆質問
面接時間が1時間以上と長い場合には、3〜5個の質問をしても問題ありません。逆質問の時間を長めにとれるので、質問で理解を深めて自分が活躍する姿をイメージしているように見せましょう。部署内の雰囲気や男女比、年齢層など、細かいところも聞いてOKです。
逆質問は何個用意しておくべき?準備に役立つ考え方と対策


逆質問を用意しておく数は、質問したい数に+2個が目安です。集団面接では他の応募者と質問が被ることが多々あります。また、面接の流れを切るような質問は避けた方が良いからです。質問内容を深堀りした質問を用意しておくと、他の人と被ったときでも質問がしやすくなります。
たとえば「事前に身につけておいた方がよいスキルや資格はありますか?」と逆質問を準備したとしましょう。深堀りした質問として「そのスキルをどの程度まで身につけておいたら現場で役立ちますか?」のように準備しておくと、どのような場面でも対応しやすくなります。
逆質問は質問したい数に+2程度、余裕をもって準備するのがポイントです。
面接官が逆質問で見ているポイントや意図


企業が逆質問を設けるのには、企業側に意図があります。面接官が見ているポイントについて解説します。
志望度の高さ
逆質問で志望度の高さを見ています。質問の内容からどこまで興味があるのか、業界・企業研究をどこまでしているかの察しがつきます。浅くどこでも使える質問だと志望度が低いと思われることがあります。
そのため、質問の仕方には企業にあわせた工夫が大切です。
適性があるか
職場や業務への適性があるかを見極めています。質問の内容で何に関心があるのか、仕事に対する考え方がわかります。待遇面の質問ばかりをすると、待遇だけで企業を選んでいて「他社でもいいのでは?」と思われることも。
コミュニケーション力
逆質問でのやり取りではコミュニケーション力もチェックしています。質問の仕方や受け答えで、ビジネスマナーやコミュニケーション力が確かめられます。話の流れを受けて、自然な流れで関連する質問ができるかが大切です。
「差し支えなければ」などのクッション言葉を適切に使えると評価が高くなります。
逆質問を考えるときの5つのポイント
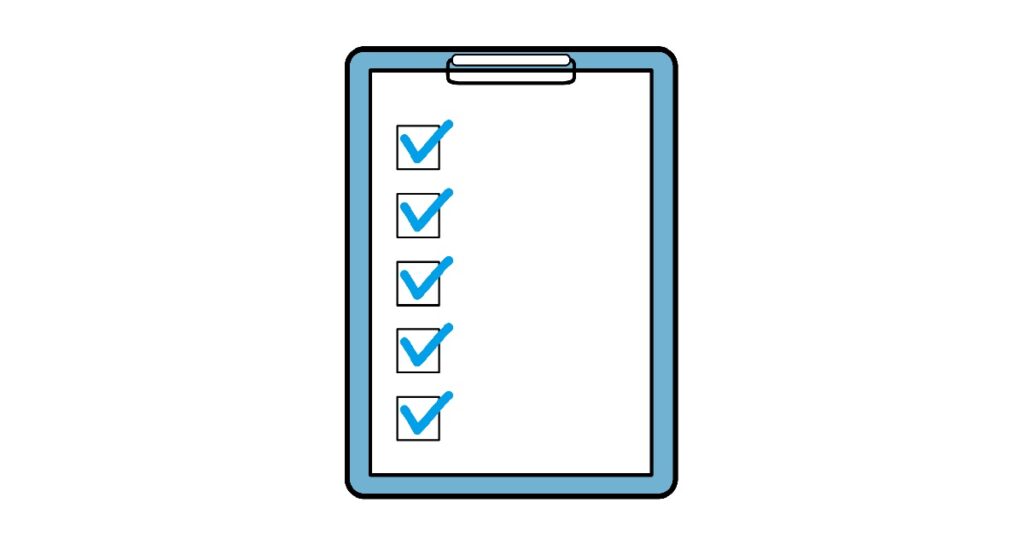
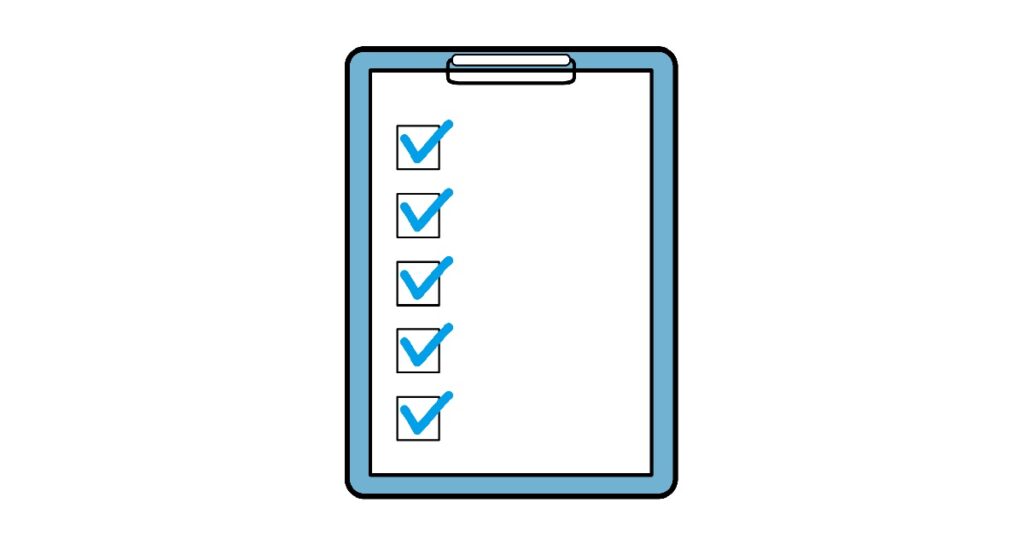
逆質問を用意するときには下記ポイントを踏まえておきましょう。
- 知りたいことを軸にする
- 志望度の高さが伝わる質問にする
- 条件面だけを聞かない
- 調べればわかることは避ける
- 回答しやすい質問にする
それぞれ詳しく解説します。
知りたいことを軸にする
知りたいことを軸にして質問を考えましょう。逆質問は、応募者がわからないことや不安なことを解消するための時間です。女性が長く働きたいと考えているのであれば、柔軟な働き方ができる制度について具体的に質問してもよいでしょう。
不安なまま入社してもミスマッチを招き、双方にとってプラスにはなりません。
志望度の高さが伝わる質問にする
志望度の高さが面接官に伝わる質問もおすすめです。逆質問の内容は、他の応募者との志望度の違いがわかりやすい傾向です。志望理由はほとんどの人が対策をしてくるため、違いや本質が見えづらくなります。
逆質問の内容で、本当の志望度の高さが見えやすくなり、好印象に繋がりやすいです。
条件面だけを聞かない
逆質問は条件面の質問だけにしないようにしましょう。条件だけで企業を選んでいるように思われる可能性があります。条件面の質問がNGなわけではありません。給与や休暇などの条件を質問するときには、志望度の高さが伝わる質問とセットにしましょう。
調べればわかることは避ける
自分で調べればわかるような質問は避けましょう。事前のリサーチ不足が相手にわかり、志望度が低く見えることがあります。企業サイトや求人情報に掲載されている内容はNGです。隅々までサイト内を読み込む必要があります。具体的な職場の雰囲気や評価制度の運用方法など、調べてもわからないことを質問しましょう。
回答しやすい質問にする
面接官が回答しやすい質問を心がけましょう。「御社の強みと弱みを教えてください」といった答えづらい質問は、面接官を困らせるだけです。「御社の将来ビジョンはどのようにお考えですか?」のような抽象的な質問は面接官が答えづらい内容です。
質問によっては場が固まるリスクもあります。
逆質問をするときの3つの注意点
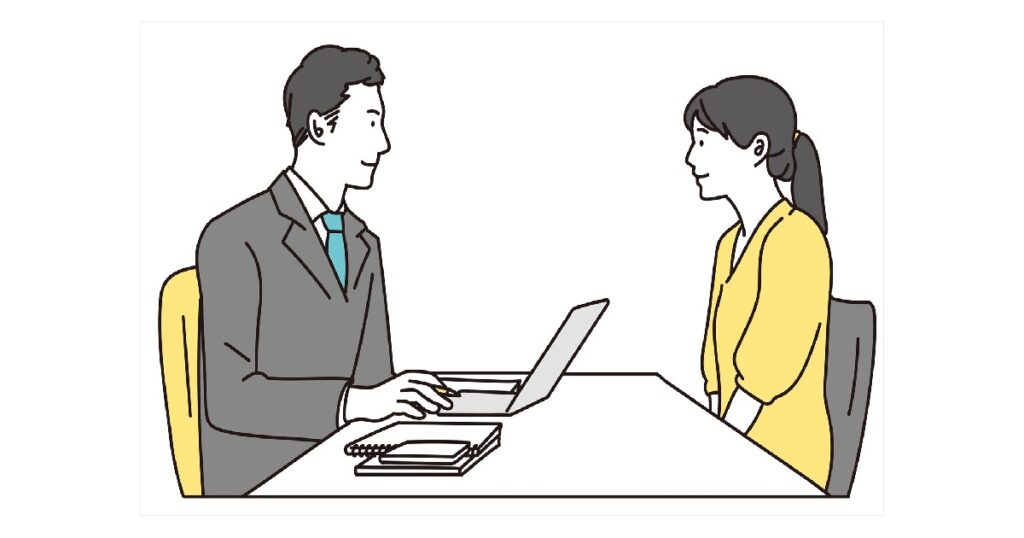
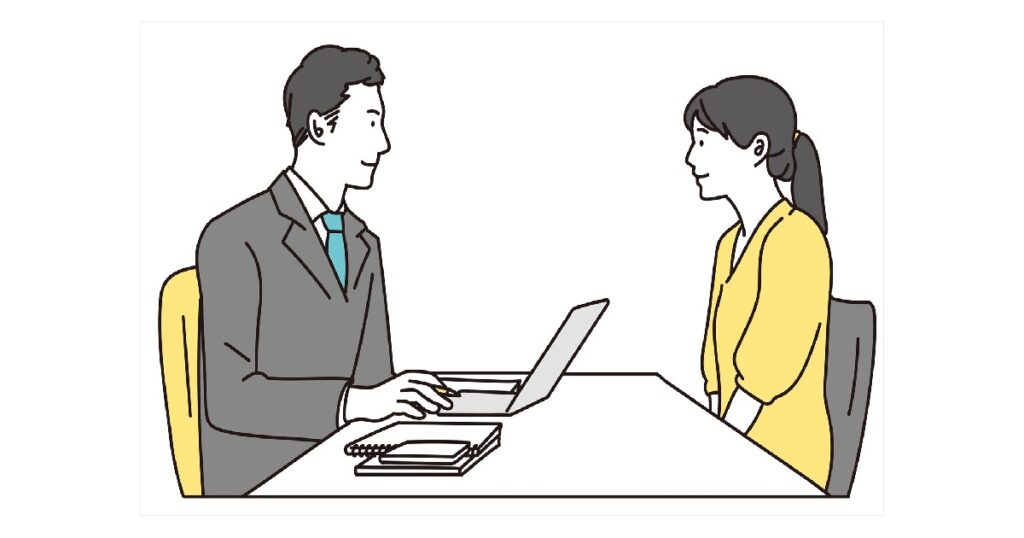
逆質問をするときにも注意することがあります。
最初に質問が何個あるか伝える
最初に質問が何個あるかを相手に伝えましょう。面接官も気持ちの準備ができます。「〇点質問させていただきたいのですがよろしいでしょうか。」と前置きをするとスムーズに進みます。
説明された内容は質問しない
事前に準備をしていた質問だとしても、説明された内容は質問しないようにします。話を聞いていないとネガティブになる可能性があります。
もし準備していた質問が、先の説明が答えになっているようであれば無理に質問する必要はありません。
質問ゼロは避ける
質問ゼロは出来る限り避けましょう。「当社に興味がないのかな」と面接官からのマイナスイメージに繋がります。ゼロ→イチにするだけでも全く違うので、出来れば1つは質問しましょう。
面接での逆質問の終わり方と印象を良くする締めくくり例
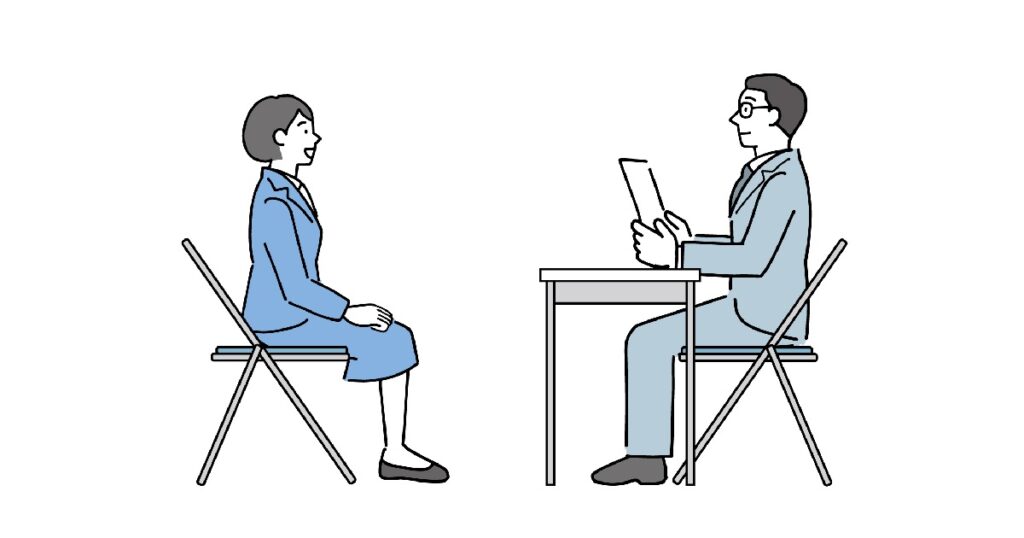
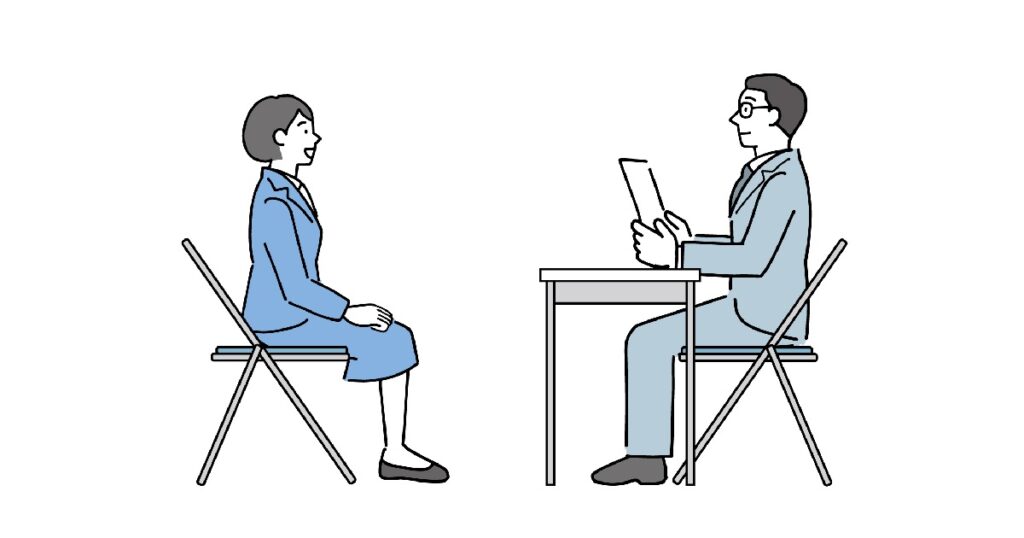
質問が終わったらどのように終わらせたら良いか疑問に思う方も少なくありません。
印象を良くするスマートな終わらせ方を知っておきましょう。
面接官にも最後の質問と伝わり心づもりができます。
質問に答えてもらったことに対して感謝を伝えましょう。
質問への回答によって理解が深まり、より入社意欲が高まったことが伝えられれば一層良い印象になります。
最後の質問への回答をもらった後の締めくくり例
ご説明いただきありがとうございました。お話を伺って、理解が深まるとともに、御社で働きたい気持ちがさらに高まりました。
逆質問の例


逆質問で質問する内容に関して、好印象になりやすい例をご紹介します。聞きたい質問が思い浮かばない方は参考にしてください。
入社後に活躍している方に共通しているスキルや資格があれば教えてください。
入社後の研修の進め方について、具体的に教えてください。
〇〇さんが実際に働かれていて、一番やりがいに感じたのははどのようなときですか?
逆質問のNGな質問例
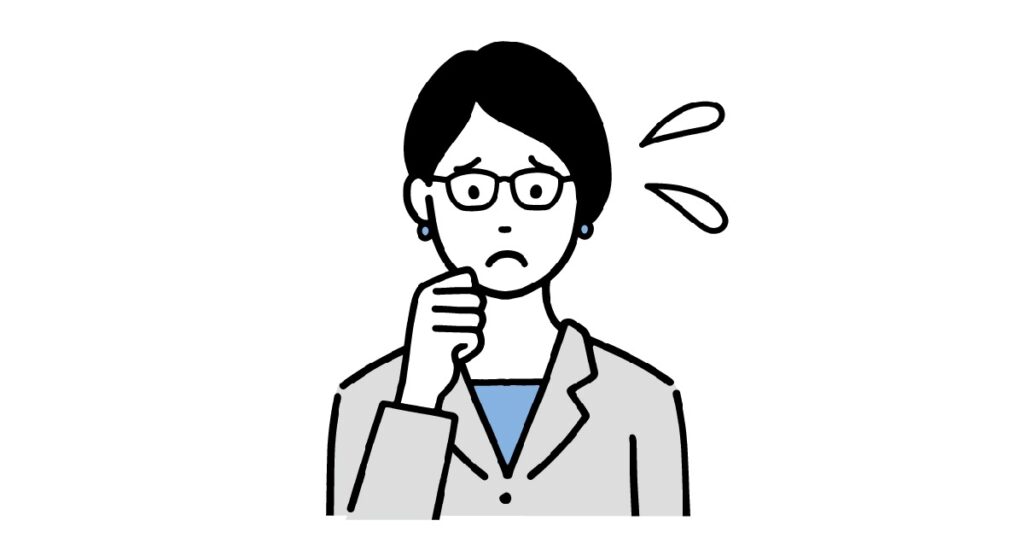
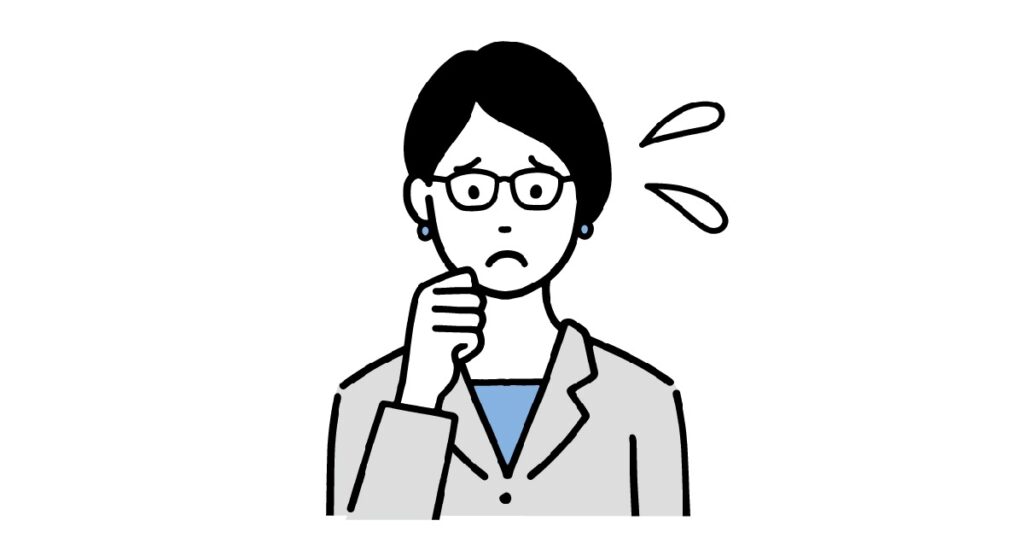
逆質問では、聞きたい内容であったとしても面接官を困らせたり、マイナスイメージに繋がる質問は避けた方が無難です。NGとなりやすい質問の例をご紹介します。
御社の事業内容を教えてください。
有給はとりやすいですか?
〇〇さんは休日何をして過ごされていますか?
よくある質問
逆質問についてよくある質問をまとめました。
- 逆質問がゼロだと落ちる?
-
ゼロ=即不合格ではありませんが「当社に興味がないのかな?」と疑問を持たれる可能性があります。質問は1つでもした方が印象が良くなります。
- 逆質問が多すぎるとどうなる?
-
面接は決められたスケジュールで進めるものなので、時間を気にせずいくつも質問をすると状況判断ができない人と見られる可能性があります。また、細かいことを気にして柔軟性に欠けると不安視される場合もあるでしょう。状況に応じた質問数の調整がポイントです。
- 逆質問の数が少なくなったときのフォロー方法は?
-
疑問点が丁寧に説明してもらったことによって解消されたと伝えられれば、相手も悪い印象にはなりません。丁寧に説明してもらったことへ感謝を伝えましょう。
まとめ
この記事では、逆質問の適切な個数について解説しました。
面接の段階や時間によって、逆質問の数は個数を調整するのがコツです。相手の都合を考えて場の雰囲気が読めるとアピールに繋げられます。
面接にむけて「質問したい数+2」の逆質問を準備しておきましょう。