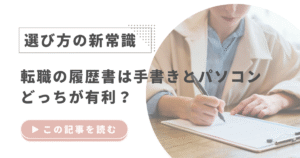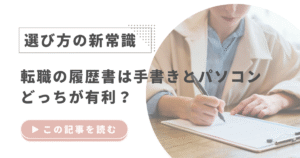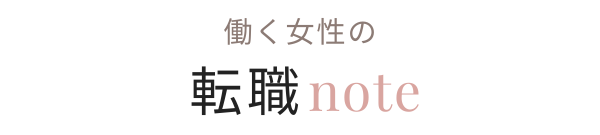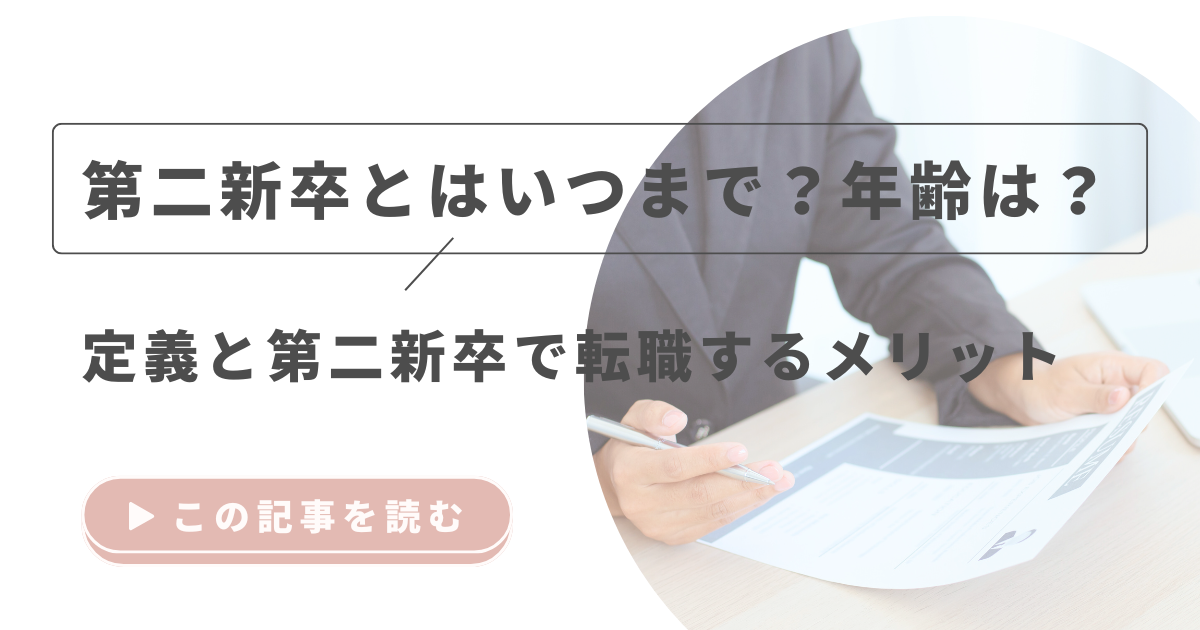第二新卒は何歳まで?25歳?27歳?



第二新卒の転職は難しい?



第二新卒で転職するメリットはある?
このような疑問がある方も多いのではないでしょうか。「第二新卒歓迎」とする求人は多いですが、明確な基準がわからず条件に当てはまるか不安ですよね。
「第二新卒」に明確な基準はありませんが、一般的に「新卒で入社後3年以内の転職者」を指します。ただし、企業により捉え方や基準に違いがあります。
この記事では、第二新卒の定義や年齢、第二新卒で転職するメリット、デメリットと解決策について解説します。
最後まで読めば、あなたが第二新卒に該当するかがわかり、希望通りの転職をかなえる一歩を踏み出せるでしょう。
本記事のライター:伊藤えま
採用・人事歴10年以上。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)取得済み。採用統括責任者として現場で得てきたリアルな知見を、発信している。
第二新卒とは?定義と年齢を解説


求人を探していると「第二新卒歓迎」の記載を頻繁に見かけるでしょう。ここでは、第二新卒の定義と似ている言葉との違いについて解説します。
第二新卒の年齢は何歳まで?
第二新卒について、法律で定められた定義はありませんが一般的に「新卒で入社後3年以内の転職者」を指します。そのため、最終学歴により目安となる年齢は異なります。
最終学歴による年齢目安
| 大卒の場合 | 25歳まで |
| 大学院卒の場合 | 27歳まで |
| 高卒の場合 | 21歳まで |
これらの年齢はあくまでも目安です。近年では、少子化により若い働き手が減少しており、20代後半あたりまでを第二新卒の対象とする企業も増えています。したがって、企業によって捉え方や基準に違いがあります。
第二新卒と新卒・既卒・第三新卒の違い
第二新卒と同じように求職者の立場を指す言葉がありますが、それぞれ対象となる人は異なります。企業が採用したい人物像を把握するために違いを理解しておきましょう。
| 第二新卒 | 新卒で入社後3年以内に転職を希望する人 |
| 新卒 | 大学・大学院・高校などを卒業見込みの学生 |
| 既卒 | 学校を卒業したものの正社員として就職した経験がない人 |
| 第三新卒 | 博士課程を修了したものの正社員としての就労経験がない人 |
| 新卒で入社後3年以内に2回以上転職をした人 |
第三新卒は、第二新卒と比べると定義が定まっておらず企業により捉え方に大きく違いがあります。
既卒には、正社員歴がなくアルバイトや契約社員、派遣社員で働いている人も含みます。厚生労働省が「新卒採用は少なくとも卒業後3年間は応募できるようにする」指針を企業に向けて出しました。そのため、既卒者を新卒採用で選考する企業も増加しています。
出典:厚生労働省ホームページ
第二新卒歓迎は何歳まで?年齢で悩んだ時の判断


第二新卒は入社後3年以内の転職者となり、大卒の場合は25歳までが目安です。「第二新卒歓迎」とする求人は増加傾向ですが、26歳や28歳の方は第二新卒に該当しないとして応募をためらうこともあるかもしれません。
応募するか迷ったときは、とりあえず応募してみるのがおすすめです。
第二新卒の年齢はあくまでも目安であり、厳密に年齢制限を設けているわけではありません。さらに、年齢だけで合否を決定することはほぼなく、スキルや経験、人柄など総合的に見て判断します。
「第二新卒歓迎」は、企業が第二新卒を積極的に採用するとの意思表示で「第二新卒しか採用しない」との限定的な募集ではありません。もし、希望する求人に「第二新卒歓迎」と書かれていても、年齢を理由に諦める必要はなく、スキルや経験、入社後の成長意欲でアピールできます。
第二新卒で転職する3つのメリット


第二新卒のタイミングで転職するのにはメリットがあります。
- 未経験でも挑戦しやすい
- 自分に合う会社を探しやすい
- 希望職種に就きやすい
項目ごとに詳しく見ていきましょう。
未経験でも挑戦しやすい
1つ目のメリットは、未経験の業種や職種に挑戦しやすいことです。
第二新卒の転職は、経験やスキルだけではなく、将来性(ポテンシャル)が評価されるため、未経験の仕事にチャレンジしやすい絶好のタイミングと言えます。特定の企業文化に染まっていない柔軟性が評価され「自社で育成したい」と考える企業も多く見られます。新しい環境にもスムーズに馴染めるため、第二新卒は育成しやすい人材として期待されているのです。
年齢が上がるごとに、経験やスキルを重視されるようになるため、未経験分野への転職は難しくなります。今後の将来性ではなく「現在の段階で何が出来るのか」が重要視される傾向に変わっていきます。
自分に合う会社を探しやすい
2つ目は、希望するライフスタイルに合う会社を探しやすいのがメリットです。
新卒の就職活動と比較して、社会人経験を経ているため、理想とするライフスタイルの解像度があがっています。自分に合う条件が明確になっているため、期待通りの会社を探しやすくなっています。
たとえば「週に2回程度のリモートワークが認められている会社」や「フリーアドレスの職場が良い」といった明確な希望条件もあるでしょう。転職サイトや転職エージェントにより検索で使える詳細な条件が設定されています。
仕事とプライベートのバランス、求める収入、働き方(リモートワーク)など理想とする条件を明確にすることで、理想の職場と出会えるでしょう。
希望職種に就きやすい
3つ目のメリットは、転職では希望職種に就きやすいことです。
新卒の求人は、職種や配属先を限定せず入社後に配属先を決定する総合職採用が一般的です。一方、中途採用は特定の職種を限定して採用する職種別採用が主流なため、特定の職種を希望する場合には大きなメリットになります。
新卒では入社後の配属先は、本人の希望だけでなく、適性や人員の状況により決定します。そのため、希望する所属先となるかは、配属先発表までわかりません。近年、希望とのミスマッチを防ぐため、新卒でも職種別採用を導入する企業は増えていますが、依然として現在でも総合職採用が主流になっています。
エンジニアやマーケティングなど特定の職種を希望するのであれば、第二新卒のタイミングでキャリアチェンジするのもおすすめです。
第二新卒の転職はやめとけ・やばいって本当?よくあるデメリットと解決策
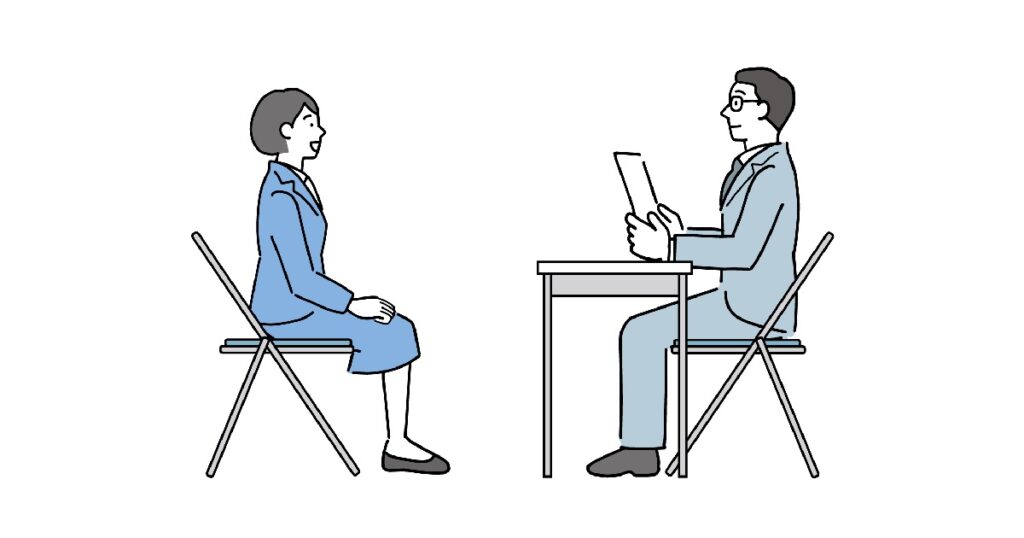
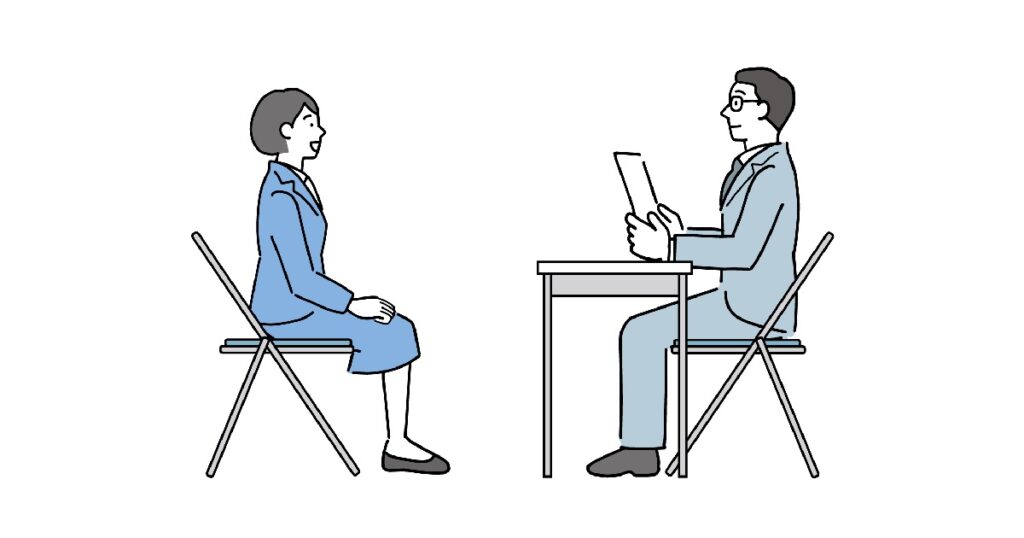
第二新卒の転職には、未経験での挑戦のしやすさや希望職種に就きやすいことなどのメリットがあります。しかしながら「やめとけ」「やばい」と言われることもあります。このように言われる原因は、第二新卒での転職にはデメリットもあるからです。ここでは、よくあるデメリットと解決策について解説します。
短期離職を懸念される
1つ目のデメリットは、短期離職を懸念される点です。
在職期間が短いと「またすぐに辞めるのでは」と懸念されることがあります。協調性や忍耐力が足りずに退職したと捉えられるリスクがあるためです。第二新卒は一般的に「入社後3年以内の転職者」となり、在職期間が短くなりがちです。ところが「第二新卒歓迎」の求人でも、面接官により短期離職を不安視されることもあります。
転職理由を「〇〇が嫌だったから」とネガティブにするのではなく「〇〇がやりたかった」とポジティブに言い換えるのが成功の鍵です。理想の実現のための転職であれば、前向きな転職として短期離職を懸念されるリスクは大幅に減るでしょう。
スキルや経験が不足している
2つ目のデメリットは、スキルや経験が不足していることです。
中途採用は、基本的に即戦力となる人材が求められています。第二新卒は社会人経験の少なさから、スキルや経験が不足していると判断され、不利になることがあります。企業によっては、研修が整備されておらず、経験が浅い社員の受け入れ体制が整っていない場合もあります。そのような会社では、豊富な経験がある応募者の方が採用で有利となりやすい傾向です。
解決策として、企業研究の徹底が効果的です。応募先で求められる人物像を、募集要項や企業のホームページで見極め、スキルや経験以外の若手ならではの積極性や柔軟性をアピールすると良い印象に繋がります。
第二新卒が転職を成功させるポイント
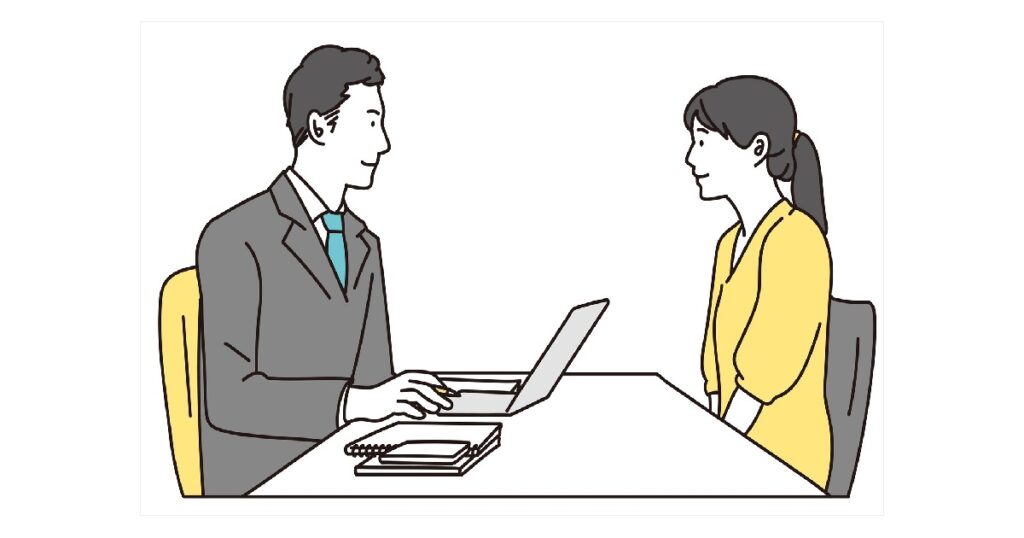
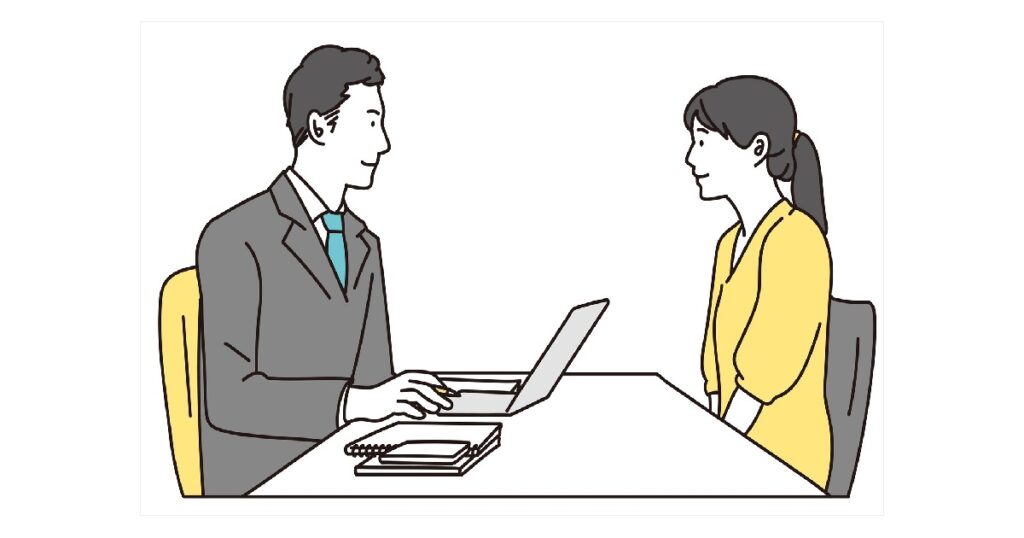
第二新卒での転職を成功させるためのポイントがあります。
- キャリアプランを明確にする
- 退職理由はポジティブに言い換える
- 転職エージェントを活用する
それぞれのポイントを解説します。
キャリアプランを明確にする
キャリアプランとは、仕事や働き方の将来的な理想像を考え、実現するためのスキルや経験を身につけるために立てる計画です。3年後・5年後・10年後どのようになっていたいかを具体的にイメージしましょう。
キャリアプランを明確にすることで、応募先を選ぶための「ぶれない軸」ができるため、応募先選びに一貫性が生まれます。そして、志望動機や退職理由の説得力が増す効果も期待できるため「この会社で実現したいこと」を具体的に伝えられるようになるでしょう。会社のビジョンに適しているとして内定に繋がりやすくなります。
まずは自己分析で、自分の強みや価値観を深く掘り下げるところから始めましょう。
退職理由はポジティブに言い換える
ネガティブな退職理由を伝えると「入社後もまた不満を抱くのでは」と懸念されるリスクがあります。ポジティブな理由に言い換えることで、未来の目標をかなえるための転職と伝わり、前向きなイメージに繋がります。
特に第二新卒は在職期間が短いことから、退職理由をネガティブな内容で伝えると短期離職を懸念される可能性が高まります。そのため、言い換えは不可欠です。
転職エージェントを活用する
転職エージェントは、求職者の転職を成功させるため、入社するまで一貫してサポートしてくれるサービスです。応募先とのやり取りも代行してくれるので、はじめての転職活動でも安心して効率的に進められます。
経歴や将来のキャリアプランをヒアリングして、求人サイトに掲載していない非公開求人を含めたあなたに合う求人を厳選して紹介してもらえます。一人では探せなかった求人や思わぬ優良求人とも出会えるかもしれません。
そして、履歴書や職務経歴書の添削サービスや面接対策でアドバイスがもらえるのも大きなメリットです。対策を重ねることで自信を持って選考に臨めるようになります。
企業が第二新卒を採用する理由


企業が第二新卒を採用するには、主に以下のような理由があります。
- 将来性(ポテンシャル)に期待している
- 若手の方が固定観念が少なく育てやすい
- 新卒と比べ基本的なビジネスマナーが身についている
- 若い世代が不足している
- 求人のターゲットを広げたい
近年、新卒の離職率が高まり、若手人材の不足が課題となっています。2024年10月に厚生労働省が発表した「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)によると、高校・短大等・大学を卒業した人の3年以内の離職者が増加傾向でした。
■ 新規学卒就職者の就職後3年以内離職率 ( )内は前年差増減
【中学】50.5% (▲2.4P)
【高校】 38.4% (+1.4P)
【短大等】44.6% (+2.0P)
【大学】 34.9% (+2.6P)
出典:厚生労働省ホームページ
若手を入社させたい企業にとって第二新卒は、企業の成長に欠かせない存在です。「基本的なビジネスマナー」+「将来性」があるコストパフォーマンスが高い魅力的な人材として期待されています。
第二新卒の年齢におけるよくある質問や疑問
第二新卒の年齢におけるよくある質問や疑問をまとめました。
- 第二新卒に26歳や27歳は含まれる?
-
大卒の場合、第二新卒の目安は25歳までとされています。しかし、明確な年齢基準はないため、26歳や27歳も対象としている企業もあります。
- 第二新卒が「やめとけ」と言われる理由は?
-
第二新卒の転職にはメリットだけではなく、デメリットもあることから難しいといわれることがあります。しかしながら、多くのメリットがあるのも事実です。売り手市場が続いていることから第二新卒の転職難易度は下がっています。
- 第二新卒は年齢と卒業後の年数のどちらで判断される?
-
一般的に卒業してからの年数で第二新卒の対象になるかを判断されます。留学などの理由で卒業まで時間がかかった場合も、年齢ではなく卒業してからの年数が基準です。
- 転職は第二新卒のうちにするか経験を積んでからするかどちらが有利?
-
第二新卒と経験を積んでからの転職でどちらが良いかは、希望する職種により違いがあります。未経験職種を希望するのであれば、第二新卒の方が将来性を期待され転職しやすい傾向があります。
まとめ|第二新卒の年齢は、企業によって対象となる範囲に違いがある
この記事では、第二新卒の対象となる年齢について解説しました。
大卒の場合、第二新卒は一般的に25歳までとされています。しかしながら、若手不足を背景に企業によって対象とする年齢には違いがあります。年齢だけで合否を判断することはほぼないため、年齢を理由に応募を躊躇う必要はありません。
さっそく、転職サイトや転職エージェントを活用して「第二新卒歓迎」の求人に応募しましょう!