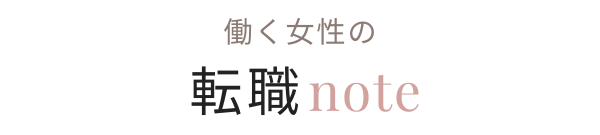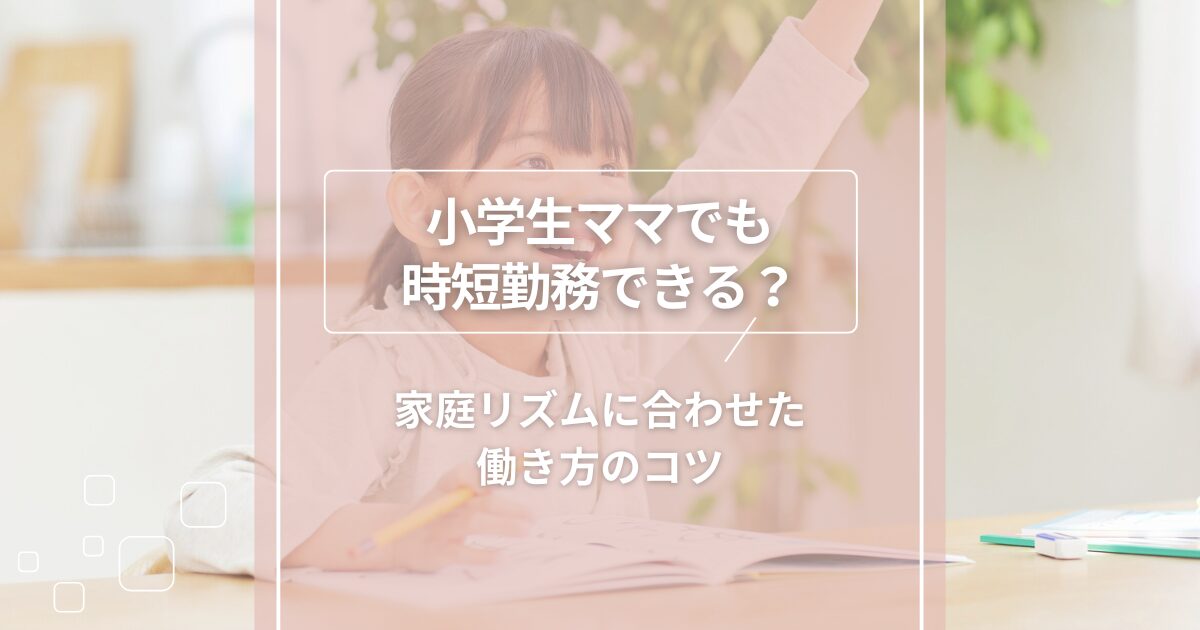- 企業に独自の延長制度があれば小学生でも時短勤務が可能
- 時短勤務以外の選択肢を知ることで、ライフステージに合わせた柔軟な働き方を計画できる
- 時短勤務継続を上司に伝えるときのポイントや理由(例文)
「小学生になったら時短勤務はもうできないの?」
「フルタイムで仕事したら、家庭と両立できる自信がない……」
「学童の時間と定時が合わない」
このようなお悩みがある方も少なくないのではないでしょうか。
実は、企業に独自の延長制度があれば、小学生になっても希望すれば時短勤務を続けられるケースがあります。
この記事では、学年別の放課後事情や、法律上・企業制度上の時短勤務の範囲、家庭とキャリアを両立させるコツ、上司への伝え方・例文までご紹介します。
最後まで読めば、小学生ママでも無理なく働き方を選び、家庭と仕事を両立するための具体的なヒントが得られるでしょう。

- 採用・人事歴10年以上
- 中途採用で900名以上を選考
- 採用統括責任者として書類選考・面接・採否の決定を担当
- 人事評価基準の策定・人事考課にも従事
- 社員のキャリア相談を多数経験
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)
小学生ママでも時短勤務はできる?学年別の対応と制度

小学校に入学すると、学童や授業の終了時間など、働くママの生活リズムにも変化があります。変化に合わせられるよう時短勤務の継続を希望する方も多いでしょう。ここでは、学年ごとの放課後事情や法律上のルール、企業ごとの延長制度について整理します。
小1・小3・小6…学年別に変わる放課後事情
小学生になると、学年によって放課後の過ごし方は大きく変わります。
- 小1
学校の授業時間は短めで、下校は午後2時〜3時頃。多くの家庭では学童保育を利用するか、家族が帰宅を待つケースが多く見られます。初めての集団生活で慣れないため、手がかかる時期です。
- 小3
授業時間が長くなり、下校は午後3時〜4時頃になることが一般的です。学童保育の利用期間が小3で終了する場合もあり、放課後の過ごし方を見直す家庭が増えます。習い事や宿題の時間も意識する家庭も出てきます。
- 小6
小学校最終学年になると、子どもがある程度自立し、放課後に留守番できる家庭も増えます。しかし、受験や塾など課外活動が増える時期でもあり、親のサポートが完全に不要になるわけではありません。
このように、学年が上がるにつれて子どもの自立度は増しますが、働くママの時短勤務ニーズは完全にはなくならないケースがよく見られます。
時短勤務は法律上いつまで可能?
育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを育てる労働者に対して、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務制度を企業が導入することを定めています。短時間勤務制度の導入が難しい場合、下記のいずれかの代替措置で対応する必要があります。2025年の育児・介護休業法改正により、テレワークが追加されました。
- 育児休業に関する制度に準ずる措置
- 始業時刻の変更等
- テレワーク
さらに、2025年10月1日施行の育児・介護休業法改正により、3歳から小学校就業前の子どもを育てる労働者に対しても、企業は柔軟な働き方ができる措置の導入が義務づけられました。
下記の5つから2つ以上を企業が選択して導入し、そのうち1つを労働者が選択して利用できます。
- 始業時刻などの変更
- テレワークなど
- 保育施設の設置運営など
- 養育両立支援休暇の付与
- 短時間勤務制度
出典:厚生労働省ホームページ
3歳未満の子どもを育てる従業員は希望すれば時短勤務を利用できます。また、3歳から小学校就業前の子どもを育てる従業員は、企業が短時間勤務制度を選択していれば利用可能です。
企業によって違う!時短勤務を延長できる制度とは
時短勤務は法律上、原則として3歳未満まで、企業の選択した措置により小学校就業前までです。ですが、企業によって独自の延長制度を設けている場合があります。
たとえば、小学校3年生や小学校卒業まで、期限を設けないケースがあります。特に「小1の壁」と呼ばれる、小学校入学による仕事と子育ての両立が難しい状況に対応できるよう、企業は制度の導入を進めています。
こうした制度は、企業ごとに異なるため、延長を希望する場合は、就業規則や人事担当者に確認しましょう。
小学生ママが時短勤務を続けるメリット・デメリット

小学生になっても時短勤務を続けるかどうかは、収入や時間の都合もあり、働くママにとって大きな判断になります。ここでは、家庭や子どもにとってのメリット、キャリアや収入面でのメリットを見ていきましょう。
家庭・子どもにとっての4つのメリット
時短勤務を続けることで得られる家庭面のメリットには、以下のようなものがあります。
- 放課後の時間に余裕ができる
学童や習い事の送迎、宿題の確認など、子どもに向き合う時間が確保しやすくなります。
- 親子のコミュニケーションが維持できる
下校後の時間を一緒に過ごすことで、子どもの学校生活や心の変化に気づきやすくなります。
- 緊急対応がしやすい
体調不良や学校行事など、急な対応が必要な場合でも柔軟に動けます。
- 生活リズムが安定する
子どもに合う起床・就寝時間や食事リズムを保ちやすく、家庭全体のバランスが整います。
このように、家庭や子どもにとってのメリットは、親子関係の質にもつながります。
キャリア・収入面での4つのデメリット
一方、時短勤務には、キャリアや収入面でのデメリットも存在します。
- 給与・賞与がフルタイムより少なくなる
勤務時間が短いため、時間外手当や昇給にも影響する場合があります。
- 昇進や評価に影響する可能性
時短勤務で業務量が制限されると、成果をアピールしづらく、昇進や昇格が難しくなる企業もあります。
- フルタイム社員との情報格差
会議や社内イベントの参加が制限される場合、情報伝達や人脈構築に差が生じることがあります。
- 長期キャリア形成のタイミング
時短勤務を選ぶことで、キャリア形成のスピードや経験の幅に制限が出る場合があります。
これらのデメリットを理解したうえで、自分や家庭にとって何を優先するかを考えましょう。
小学生ママが時短勤務を続けるか迷ったときの判断ポイント
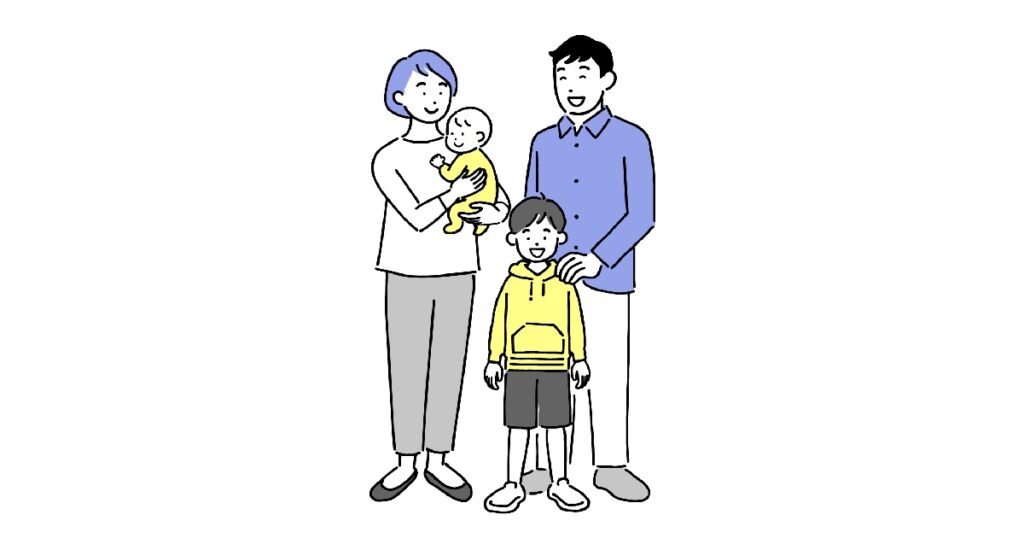
子どもが小学生になると、時短勤務を続けるかフルタイムに戻るか迷うママは多いのではないでしょうか。ここでは、生活のリズムや家庭環境、キャリア・職場評価の観点から判断のポイントを整理します。
生活リズム・家庭環境から考える
小学生ママが時短勤務を続けるかは、まず家庭の生活リズムや子どもの環境に合わせて判断しましょう。子どもの放課後の過ごし方や習い事など、家庭ごとの事情が働き方に大きく影響します。
たとえば、小学校低学年の子どもはまだ放課後の留守番が難しく、保護者の帰宅時間が早い方が安心です。配偶者の勤務時間との調整も必要で、家庭内で無理のないスケジュール作りが不可欠です。一方、子どもが高学年になり自分で留守番ができるようになれば、勤務時間を少し延ばしてフルタイムに近い働き方を検討できるでしょう。
生活リズムや家庭環境を軸に考えることで、無理なく仕事と育児を両立できる働き方を選ぶ判断材料になります。
キャリア・職場の評価への影響
時短勤務を続けるか判断する際には、キャリアや職場での評価への影響も考えましょう。
勤務時間が短くなることで、担当できる業務量やプロジェクトが制限される場合があります。昇進や昇格のタイミングで「経験不足」と評価されるリスクは無視できません。また、職場内で目立つ成果やリーダーシップ経験が得られにくくなることも、長期的なキャリア形成に影響を与える可能性があります。
フルタイムの同僚が多くの実績を重ねる一方で、時短勤務の社員は担当業務が絞られ、評価される機会が限定されることもあるかもしれません。
時短勤務の延長をする際は、家庭との両立だけでなく、職場の評価制度やあなたの将来的なキャリア目標を考慮した上での判断が大切です。
小学生ママの働き方を支える時短勤務以外の選択肢
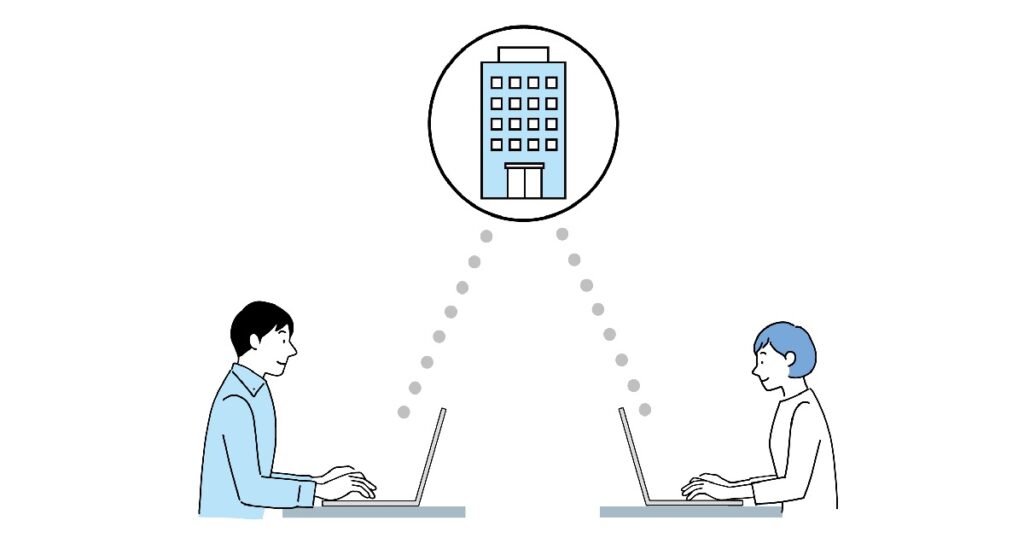
多様な働き方が普及した現在、時短勤務以外の働き方を選ぶママも増えています。ここでは、キャリアを重視したい場合と家庭との両立を優先したい場合、それぞれに合った働き方をご紹介します。
キャリアを続けたい人に合う働き方【フレックス・リモート・転職】
キャリアを途切れさせず働きたい場合、時短勤務以外に以下のような選択肢もあります。
- フレックスタイム制度
出勤・退勤時間を自由に設定できるため、学童のお迎えや家庭の予定に合わせやすくなります。
- 在宅勤務・リモートワーク
通勤時間を削減でき、子どもの世話や家事との両立がしやすいのが特徴です。近年、企業によっては出社と在宅をあわせた勤務が可能なケースも増えています。
- 転職
現在の職場で子育てとの両立が難しい場合、転職して環境を変えることが唯一の解決策となることもあります。
これらの方法は、勤務時間はフルタイムでも、場所や時間の調整で働きやすさを確保できる点がメリットです。
家庭との両立を重視したい人向けの働き方【パート・フリーランス】
一方、家庭との両立を優先する場合は、勤務形態を柔軟に変える選択肢もあります。
- パート勤務
勤務時間を短くして家庭に合わせることで、子どもとの時間や家事の負担も減らせます。働くママが多い職場では、緊急時にも理解が得やすい利点もあります。
- フリーランス・業務委託
仕事量やスケジュールを自分で自由に調整できるため、子どもの予定に合わせやすくなります。
家庭との両立を重視する場合は、収入の変化や社会保険加入の有無を確認しながら、自分に合う働き方を選びましょう。時短勤務以外の選択肢を理解しておくことで、ライフステージに応じた柔軟な働き方のプランが立てやすくなります。
職場とのトラブルを防ぐ!小学生ママが時短勤務を続けやすくする3つのコツ

時短勤務は子育てと仕事を両立する上で助けになる制度ですが、職場との認識のズレやトラブルがあると続けにくくなります。ここでは、実践しやすい3つのコツをご紹介します。
同僚との関係づくり・信頼の築き方
時短勤務を続ける上で、同僚との良好な関係を築くことは大切です。勤務時間が短い分、同僚に業務の負担が偏る場合があります。日頃からコミュニケーションを取り、感謝や配慮を示すことで、信頼関係を構築できます。
朝や終業時に短くても声をかけて情報共有したり、助けてもらった場合は感謝をこまめに伝えると良いでしょう。また、進捗連絡を徹底し、周囲があなたの状況を把握できるようにすることも連携強化に役立ちます。さらに、チームの会議やイベントには可能な範囲で参加するのも効果的です。
時短勤務中でも同僚との関係づくりや信頼維持の意識で、業務を円滑に進めながら、職場での居心地や相手への配慮を維持できます。
業務効率を高めるタイムマネジメント
限られた時間で最大限成果を出すための工夫もポイントです。
- 優先順位を明確に
重要なタスクとそれほど急ぎではないタスクを分け、効率よく対応します。
- 業務の見える化
進捗や担当業務の共有で、管理者が全体を把握しやすくなり、生産性が向上します。
- 定時内での集中した作業
集中できる時間帯を把握して取り組む順番を変えることで、短い勤務時間でも成果を出しやすくなります。一般的に午前中が集中しやすい時間帯とされています。
時短勤務継続を上司に伝えるときのポイントや理由・例文
時短勤務を継続したい場合は、上司への伝え方を工夫しましょう。単に「子どもが小学生だから時短勤務を続けたい」と伝えるだけでは、必要性がわかりづらく、理解や承認を得にくくなります。
上司に納得してもらうためには、業務への影響を最小限にする工夫や、自分が貢献できるポイントを合わせて伝えることが効果的です。
例文
子どもが小学生になりましたが、まだ一人で留守番できないため、引き続き時短勤務を希望しています。現在の業務はチームと調整し、納期に影響が出ないよう優先順位をつけて対応しています。必要に応じて、リモートやフレックスも活用して効率を上げ、チームに負担をかけないよう努めます。
時短勤務継続の理由と業務への配慮を具体的に伝えることで、上司から納得してもらい、協力を得やすくなります。
小学生ママの時短勤務についてよくある疑問Q&A
小学生ママの時短勤務についてよくある質問をまとめました。
- 時短勤務を続けると昇進できないって本当?
-
時短勤務が昇進に影響するかは企業により異なり、必ずしも昇進できないわけではありません。ただし、フルタイムの方に比べて経験や案件参加の機会が少なくなるリスクがあります。上司や人事と定期的に面談を行い、あなたの目標と会社の評価基準をすり合わせましょう。
- 子供が放課後留守番できるようになったら、フルタイムに戻すべき?
-
子どもが一人で留守番できる年齢になった場合でも、無理にフルタイムに戻す必要はありません。学童が不要になっても、朝や夕方の時間を家庭で過ごすために時短勤務を継続しているママは多くいます。会社の制度や評価に問題なければ、自分に合った働き方を優先して選びましょう。
まとめ|小学生ママの働き方は“無理なく続ける”が正解
この記事では、小学生ママの時短勤務について解説しました。
小学生ママが仕事と家庭を両立するには、時短勤務の活用が大きな助けになります。育児・介護休業法の改正により、両立しやすい環境が導入されました。ただし、法律や制度だけでなく、家庭の状況や職場環境に合わせた選択が大切です。
時短勤務を上手に活用しながら、キャリアも家庭も無理なく両立できる環境を整えていきましょう。