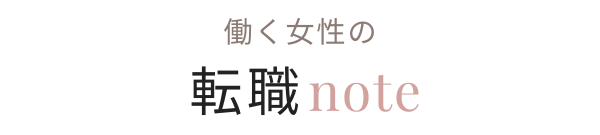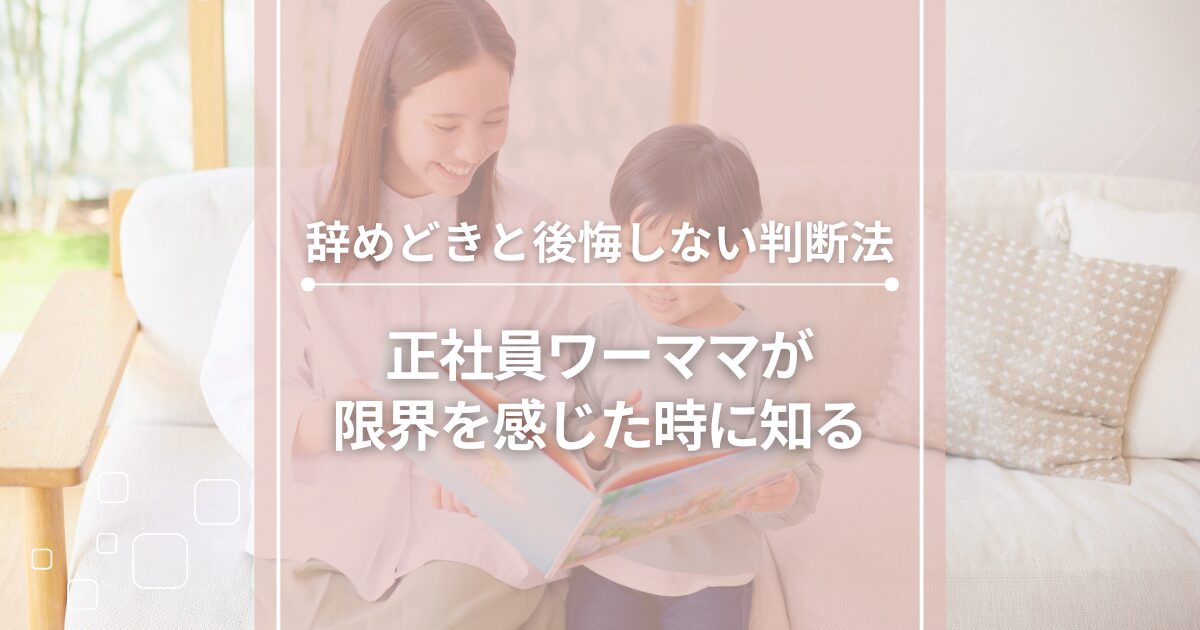- 正社員ワーママはトリプルでの負担
- 2025年改正の育児介護休業法でワーママの働きやすい環境が整備される
- 限界を迎えた時の判断と選択肢を知っておく
「仕事と育児・家事の両立で心身が限界……」
「正社員ワーママとして続けるべきか悩む」
「退職したらもったいない?」
こんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、正社員ワーママが「限界」と感じる主な理由を整理し、健康・家族・キャリア・職場制度の4つの視点で後悔しない判断法を解説します。さらに、2025年改正育児介護休業法での変更点もわかりやすくご紹介します。
最後まで読めば、心身の負担を減らしつつ、家族と自分の幸せを両立させる選択が見えてきます。

- 採用・人事歴10年以上
- 中途採用で900名以上を選考
- 採用統括責任者として書類選考・面接・採否の決定を担当
- 人事評価基準の策定・人事考課にも従事
- 社員のキャリア相談を多数経験
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)
正社員ワーママが「限界」「もう無理」と感じる4つの理由
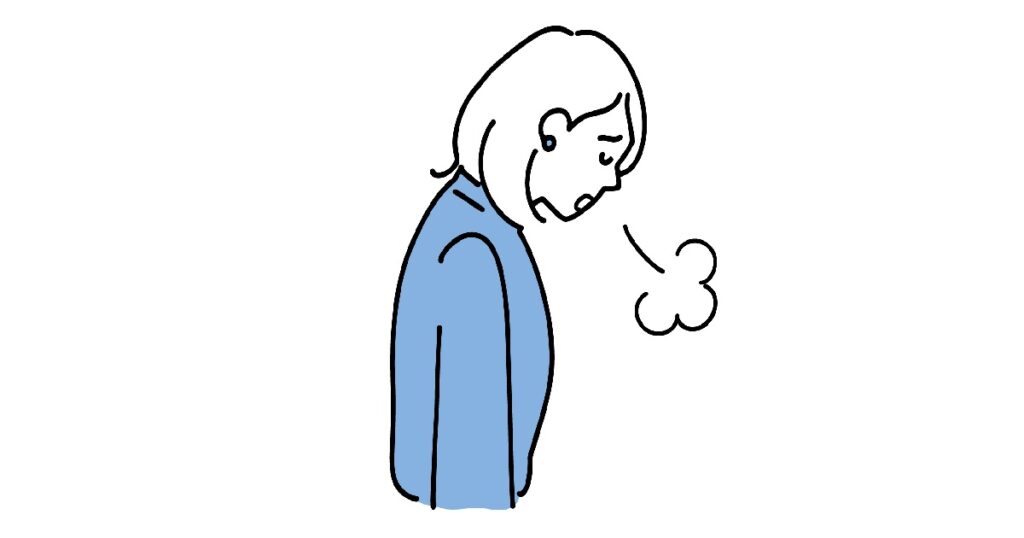
働く母親として、正社員の仕事と育児・家事の両立は重い負担となり、多くのワーママが日々「もう無理かも」と感じる瞬間があります。限界と感じる主な理由は以下のようなものがあります。
- 仕事と育児・家事のトリプル負担
- 周囲の理解やサポート不足
- 心身の疲れ・ストレス・メンタル崩壊
- 「ワーママは甘えるな」との社会的プレッシャー
項目ごとに詳しく見ていきましょう。
仕事と育児・家事のトリプル負担
働く母親の一日は、朝から夜まで休む暇がほとんどありません。朝は子どもの着替え、朝食、自分の出勤準備、送り出しで、日中は会議や書類作成など業務に追われます。帰宅後は夕食の準備、子どもの宿題、入浴、寝かしつけと、ほとんど休む時間がないまま1日があっという間です。
週末も掃除や買い物など家事に追われるため、自分の時間を作ることも難しく、リフレッシュする時間は限られています。特に、小学校入学前の子どもを抱えるワーママは、夜中の授乳や夜泣きの対応で睡眠不足が続くことも多く、退職・精神力ともに限界に近づきます。
こうしたトリプル負担は、働き続ける中で「もう無理」と感じる要因の1つです。
周囲の理解やサポート不足
ワーママが限界を感じる理由の2つ目は、職場や家庭の理解不足があります。周りからの協力や理解が得られないとストレスを感じやすく、辛く感じる場面が増えます。
たとえば、以下のような状況です。
- 上司や同僚が育児の大変さを理解していない
- 家事・育児の負担が家庭内で偏っている
- 時短勤務や在宅勤務制度があっても使いにくい
サポート不足の環境では、相談しても相手からの理解が得られず、孤独感が増してしまいます。職場や家庭のサポート不足は、精神的な疲弊を早め、限界を感じる原因になります。
適切な支援や理解を得られる職場を選び、家庭環境を作ることが不可欠です。
>> 静かな退職の原因は?背景や心理的理由をわかりやすく解説
>> 職場での女性の人間関係が怖い・疲れる…回避とストレスゼロのコツ
心身の疲れ・ストレス
限界を感じる3つ目の理由は、心身の疲れやストレスが原因です。長時間労働や家事・育児の負担が蓄積すると、心身に深刻な影響を及ぼします。
具体的には、慢性的な疲労、不眠、集中力の低下、気力の減退などが現れ、イライラや不安感が増すことがあります。心身が疲弊した状況が続くと、仕事や家庭生活に支障がでるほどのメンタル崩壊の状態に陥るケースも。結果として「もう無理だ」と感じて退職を選ぶこともあります。
放置は体調不良や家庭関係の悪化につながるため、早めに心身の状態をチェックし、医療機関や相談窓口の活用を状況に応じて検討しましょう。
「ワーママは甘えるな」との社会的プレッシャー
正社員ワーママが限界を感じる4つ目の理由は、周りからの社会的プレッシャーです。周囲の価値観や社会的期待も、ワーママの負担を増やす要因です。
「正社員ママは勝ち組」「だから子持ち様は」といった心ない言葉は、心理的負担を大きくします。周りに味方がいないように感じると、助けを求めにくくなり、孤独感や焦りが増します。その結果、心身にかかる負担がさらに大きくなってしまうのです。
世間の目を理解し、自分の限界を客観的に理解することが、自分を守る第一歩です。
母親のうち仕事をしている人は75.7%、正社員は30.4%
厚生労働省が実施した国民生活基礎調査によると、子どもを持つ母親の就業状況は以下の通りでした。
就業状況 割合 仕事をしている母親 75.7% うち正社員 30.4% パートなど非正規 36.4% その他 8.8% 出典:厚生労働省ホームページ「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」を加工して作成
多くの母親が働きながら家事・育児を両立していることがわかります。パートなど非正規雇用を選ぶ人の割合がやや多いものの、正社員として働く人も少なくないのが現状です。
限界を迎えた正社員ワーママが退職かを判断するための4つのチェックリスト
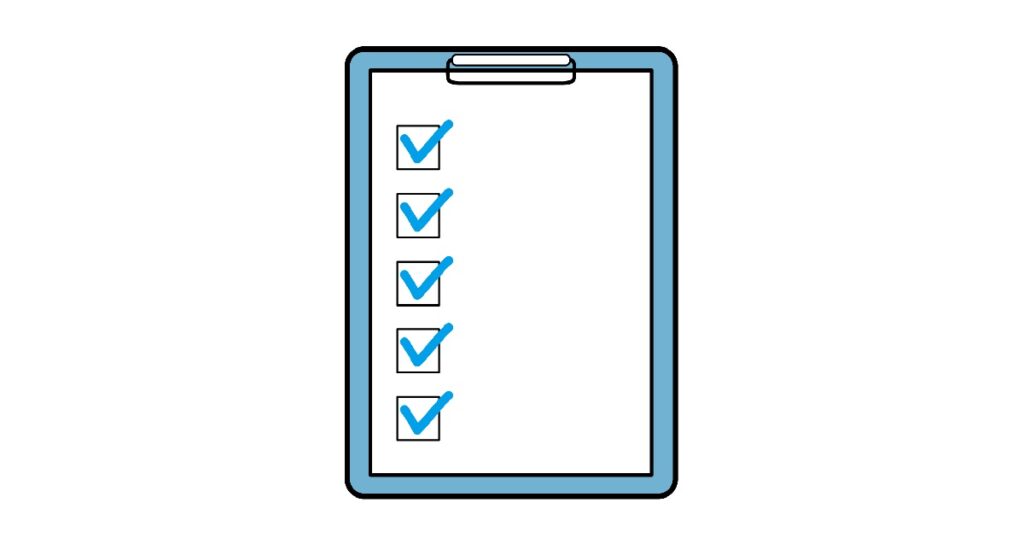
正社員ワーママとして働き続けるか、退職するかの判断は難しく、悩む人も多く見られます。ここでは、後悔しないために客観的に自分の状況を確認するチェックリストをご紹介します。心身や家庭、キャリア、職場制度の観点から整理して考えてみましょう。
健康・メンタルへの影響
体調不良や慢性的な疲労、精神的ストレスが続く場合は要注意です。回復に時間がかかる可能性もあり、家庭や仕事への影響も大きくなります。
頭痛、肩こり、睡眠不足、胃腸への不調などは、心身の「限界サイン」の一つです。精神面では、イライラや不安感の増加、仕事へのモチベーション低下、集中力の欠如などが現れることがあります。
早めに医療機関にかかり、仕事を続けられる状態なのか専門家の意見を聞きましょう。
家族や子どもへの影響
家族や子どもへの影響も判断材料の一つです。母親の心身状態は家庭全体に大きく影響します。
たとえば、以下のようなサインがある場合は注意が必要です。
・子どもとの時間が減り、コミュニケーション不足になっている
・家庭内でイライラや衝突が増えている
・子どもの生活リズムや習慣に影響が出ている
・パートナーとの関係に不満や疲れを感じる
家庭への影響を客観的にチェックすることで「働き続けることが本当に家族の幸せにつながっているか」を見極める材料になります。
キャリア・収入の見通し
正社員ワーママが退職か継続かを判断する際、キャリアや収入の見通しを明確にすることも重要です。仕事を続けるかの判断において、将来の生活や家庭への影響が大きく関わります。
正社員を続ける場合、安定した収入を得られるのは大きなメリットです。さらに、昇給や給与アップの可能性、社会保険の充実、将来の年金額も期待できます。一方、退職してフリーランスやパートに転校する場合は、収入は一時的に減少する可能性がありますが、柔軟な勤務時間で家庭との両立を得られるメリットがあります。
将来的なキャリアと収入の見通しを整理し、自分と家庭にとって最適な働き方を選択しましょう。
在宅勤務や時短制度など職場制度の使いやすさ
育児・介護に関する制度が整っているか、実際に使いやすいかも判断の重要なポイントです。制度が実際に活用しやすい環境であれば、仕事と育児・家事の両立がぐっと楽になり、精神的な負担を減らせます。
時短制度を取得したい場合、制度上は可能でも職場の雰囲気や上司の理解が乏しいと、取得しづらい場合があります。一方、制度が柔軟に使える職場では、残業時間の負担を減らし、子どもの送迎や家事の時間を確保できます。先輩社員も活用していることが多く、遠慮なく利用できるでしょう。
職場制度の使いやすさを把握し、自分が実際に利用できるのかを見定めることが、仕事を続けるかの判断材料となります。感情だけで判断せず、様々な視点から考えることで、後悔しない判断ができます。
>> 【女性向け】在宅勤務の仕事7選|メリット・デメリットと始め方
正社員ワーママを続ける場合の工夫とサポート
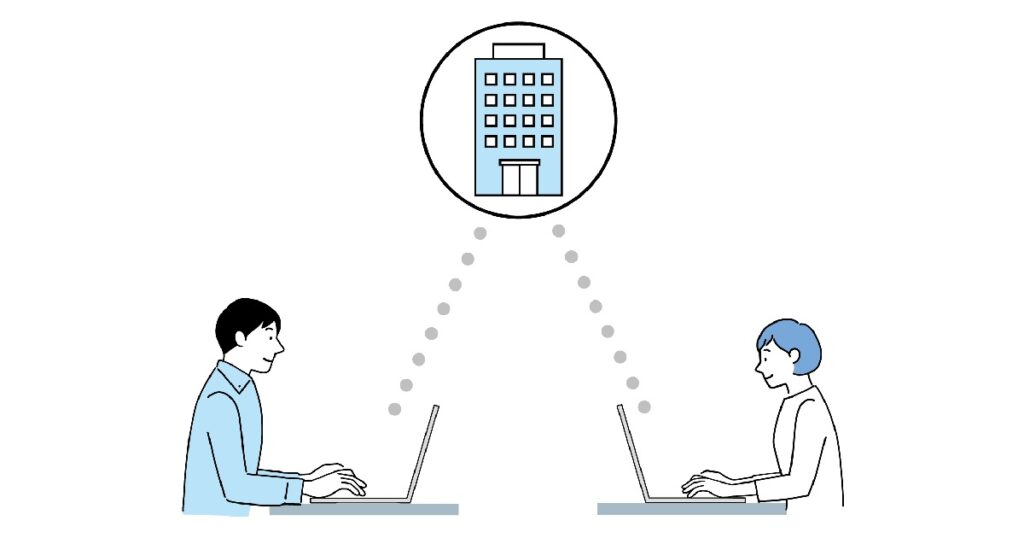
正社員として働きながら育児・家事を両立するには、工夫とサポートの活用が不可欠です。負担を減らし、心身を守りながら働き続けるための方法を解説します。
家事・育児の分担・外注
仕事と育児・家事の両立として、家事・育児の分担や外注を取り入れることは効果的です。時間には限りがあり、すべて自分一人で抱え込むと心身の負担が増し、仕事にも悪影響が出る可能性があります。夫婦や家族での家事・育児の役割分担で、一人にかかる負担を減らせます。
具体的な方法には以下のようなものがあります。
・パートナーと家事・育児の分担ルールを明確にする
・食事や掃除、洗濯などの家事を外注、宅配サービスで補う
・学童や保育園の延長保育を活用する
近年は、食材宅配などワーママにとって助かるサービスが充実しています。無理に全て自分で抱え込まず、頼れるものは頼ることも働きつづけるための戦略です。
2025年改正育児介護休業法で働きやすくなる
2025年度に施行された育児・介護休業法の改正により、働く親や介護者の支援が強化され、より柔軟な働き方が推進されるようになりました。
・子の看護休暇の対象拡大
対象年齢が「小学校3年生修了まで」に延長されました。取得事由も「病気・けが」「予防接種・健康診断」に加え、「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」などが追加されます。・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
対象が「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されました。・短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加
短時間勤務制度を講じることが困難な場合、テレワークが代替措置として追加されます。・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置義務化
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、企業は以下の5つの措置から2つ以上を選択して講じる義務が生じます。
- 始業時間等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
・個別の意向聴取と配慮義務化
妊娠・出産等の申出時と、3歳未満の子を養育する労働者に対し、勤務時間や勤務地など仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取し、その意向に配慮することが義務付けられました。・育児休業取得状況の公表義務拡大
公表義務の対象企業が「従業員300人超」に拡大され、男性の育児休業取得率などが公表対象になります。出典:厚生労働省ホームページ
改正により柔軟な働き方が導入され、正社員で働きやすい環境が整備されます。
ワーママ同士の情報交換・コミュニティ活用
同じ立場のワーママとの情報交換も大きな支えになります。悩みや工夫の方法の共有で、自分だけが大変だと思い込むストレスが軽減する効果が期待できます。
オンラインコミュニティやSNS、職場内のワーママネットワークを活用すると、子育てや仕事の両立に関する具体的なアイデアやアドバイスが得られるでしょう。共感し合える仲間がいるだけでも、安心感が生まれます。
孤立せず、必要なときは相談できる環境を整えることもポイントです。
価値観を見直す
自分の価値観を見直すことも有効です。仕事・育児・家事の優先順位を整理し、自分と家族にとって必要なことに重点を置くことで、負担を軽減できます。「キャリアを最優先にするのか」「子供との時間を優先にするか」「家事にこだわるか」といった価値観を整理しましょう。
たとえば、毎日の夕食を手作りにこだわっていたワーママが、宅配食材や家事代行を取り入れ、子どもと過ごす時間を確保しストレスを減らしたケースもあります。また、仕事の評価より家庭の安定や心の余裕を重視する選択をしたことで、前向きになれた例もあります。
仕事の価値観を明確にすることは、限界を感じやすい正社員ワーママにとって働き続けるための有効な手段です。
限界を迎えた正社員ワーママが退職・転職を考える場合の選択肢

心身や家庭への負担が大きくなり、正社員として働き続けることに限界を感じる場合、退職や転職との選択肢も視野にいれる必要があります。ここでは、現実的に検討できる選択肢を整理し、後悔のない判断に役立つ情報を紹介します。
フリーランスや在宅ワークへの転向
退職後にフリーランスや在宅ワークへ転向することで、時間の自由度や家庭との両立が大幅に向上します。Webライターやデザイナー、オンライン講師など、自宅でできる仕事は年々増加しています。
フリーランスで働く場合、通勤時間や柔軟な勤務時間を確保できる一方で、収入の不安定さや社会保険の自己負担など考慮すべき点もあります。始める前に、スキルや市場ニーズをチェックし、副業で少しずつ仕事を受けることで、リスクを抑えながら移行が可能です。
正社員で疲れたワーママは、いままでの経験やスキルを活かせるフリーランスも検討すると良いでしょう。
パート・派遣など柔軟な働き方への移行
正社員を続けるのが難しい場合、パートや派遣など柔軟な働き方ができる雇用形態に切り替える選択もあります。
メリットとポイントは以下の通りです。
・労働時間を調整でき、子育てとの両立がしやすい
・子育て中のママが多く、正社員より理解が得やすい
・収入は減る可能性があるが、家庭や自分の時間を確保できる
・労働条件や福利厚生を事前に確認し、無理のない働き方を選ぶ
無理なく仕事を続けるために、雇用形態の変更を検討してみるのも良い方法です。
退職後に「幸せ」を感じる人の共通点
退職や働き方の変更に満足しているワーママにはいくつか共通点があります。退職を単なる逃避ではなく、目的の達成ために選んでいます。
- 自分と家族の価値観を優先して判断している
- 収入より心身の健康や子どもとの時間を重視している
- 新しい働き方やスキル習得に前向きに取り組める
- 必要なサポートや制度を事前に理解して活用している
退職や転職はネガティブな理由での決断ではなく、希望に沿ったライフスタイルにするための手段と捉えることで満足感が高まります。
後悔しないために準備すべきこと
退職や転職で後悔しないためには、事前準備の徹底が欠かせません。情報チェックや現状把握で「思っていたのと違った」とのミスマッチを防げます。
事前準備として下記のことを進めましょう。
・収入や必要最低限の生活費のシミュレーション
・転職やフリーランス移行に必要なスキルの確認
・家族との話し合いで負担や期待を共有
・退職後に利用できる公的支援や補助制度の確認
情報を整理しておくことで、感情だけでの判断を防ぎ、安心して新しい選択に踏み出せます。
>> 大企業から転職しないほうがいい?後悔しない人と失敗する人の違い
まとめ|正社員ワーママが限界を迎えたら自分と家族の幸せを軸に判断しよう
この記事では、正社員ワーママが限界と感じる原因や対処法について解説しました。
正社員のワーママは、仕事・育児・家事のトリプル負担、周囲の理解不足など複合的な要因で限界と感じる場面があります。心身の負担が大きくなった場合は、退職や転職も選択肢として検討しても良いでしょう。
肝心なのは、キャリア・収入だけでなく、自分と家族の幸せを軸にした判断です。制度やサービスを活用し、無理なく自分に合った選択で、ワーママとしての生活と仕事の両立が可能になります。