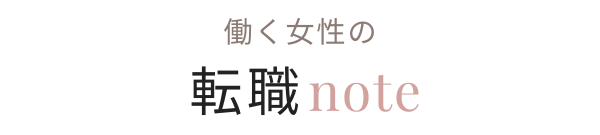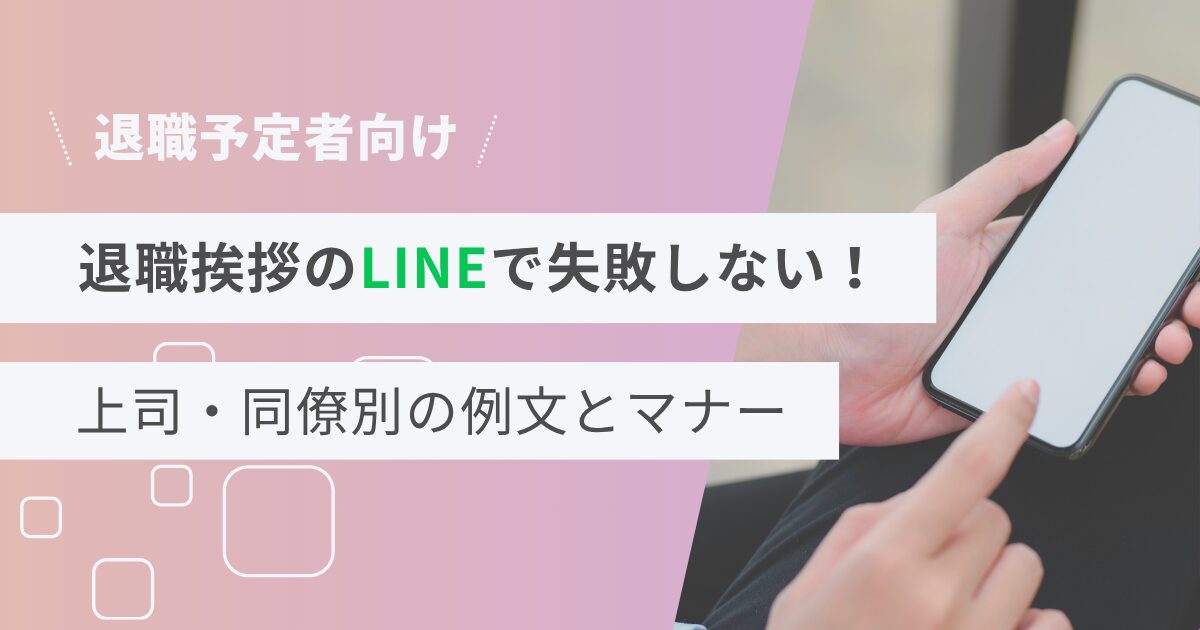「退職が決まったけど、LINEで挨拶してもいいの?」
「LINEはどこまで送るべき?」
「相手の印象を悪くしない文面が知りたい」
このような疑問がある方も多いのではないでしょうか。グループLINEや個別メッセージなど送る相手やタイミングで迷うこともありますよね。
この記事では、退職挨拶をLINEでする際の基本マナーや、上司や同僚、退職後に送る場合のすぐ使える例文、送信時の注意点を解説します。
最後まで読めば、失礼のない挨拶LINEが迷わず送れるようになります。
本記事のライター:伊藤えま
採用・人事歴10年以上。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)取得済み。採用統括責任者として現場で得てきたリアルな知見を、発信している。
退職の挨拶をLINEでするのはあり?基本マナー

退職の挨拶はこれまで「対面」や「メール」が一般的でしたが、近年はLINEで送る人も増えています。便利な反面、送り方を間違えると「失礼」と受け取られることもあるため、マナーを押さえておきましょう。
LINEで退職挨拶するケースが増えている理由
LINEが使われるようになった背景には次のような理由があります。
・職場の連絡ツールとして普及している
社内でグループLINEを活用する企業が増え、業務外のやり取りも自然に行われています。
・手軽に一斉送信できる
複数人に同じ内容を同時に送れるため、退職の挨拶とも相性が良いです。
・在宅勤務や有給消化との相性
働き方が多様化したことで直接会って挨拶ができないシーンが増えました。そのため、オンラインで完結する方法として選ばれています。
現在では、LINEでの挨拶が「失礼」ではなく「自然」だと感じる人も多くなっています。ただし、ビジネス色の強い場面や関係性では、メールや対面の補助手段と考えるのが無難です。
LINEで退職挨拶する際の基本マナー
LINEで退職挨拶を送るときは、身近さと礼儀のバランスがポイントです。LINEは手軽に送れるメリットがある一方、内容によっては失礼と受け取られるリスクもあります。相手に気持ちよく受け取ってもらえるよう配慮しましょう。
- 冒頭に退職する旨を簡潔に伝える
- これまでのお礼を一文添える
- 今後も関わりがある場合は、連絡先やSNSを伝える
- 改行を使って見やすくする
たとえば「〇月〇日をもって退職いたします、これまで本当にありがとうございました」と短くまとめた内容でも、誠実さは十分に伝わります。むしろ、長文すぎると読みづらくなりLINEのメリットを損なうため、簡潔にまとめましょう。
退職時のLINE挨拶のタイミングと送る相手

退職のとき、誰にLINEで挨拶をしたら良いのかは迷いやすい部分です。相手によって送るベストタイミングも異なるため、あらかじめ整理しておきましょう。
退職挨拶のLINEを送るべき相手
基本的には、普段からやり取りのある人や、仕事でお世話になった人に送りましょう。具体的には、上司や先輩、同僚といった方々がLINEを送るべき相手となります。
・上司・先輩・社長など立場が上の人
直接挨拶ができなかった場合、フォローとしてLINEを送ると安心です。
・同僚・同期
普段からグループLINEで連絡している場合は、自然に挨拶できます。
LINEで挨拶する場合は、敬語とフランクさのバランスを意識して、相手に合わせた文面を選びましょう。
退職挨拶のLINEを送るタイミング
LINEを送るタイミングは、送る相手によってベストなタイミングが異なります。以下のようなタイミングで送るのが一般的です。
| 相手 | 送るタイミング目安 |
|---|---|
| 上司・先輩 | 退職日の前日まで、もしくは最終出勤日の業務後 |
| 同僚・同期 | 最終出勤日の当日、勤務後に一斉送信 |
会社により挨拶するタイミングに慣習が存在する場合もあります。先に退職した方から受け取ったメッセージでタイミングを確認するのも良いでしょう。
最終出社日から有給消化をして退職をする場合は、最終出勤日が挨拶をするベストタイミングです。タイミングを見計らって送ることで、感謝の気持ちがより伝わりやすくなります。
退職挨拶のLINEを送らなくてもよい場合
LINEでの挨拶が必須ではないケースもあります。既に直接挨拶を済ませた相手、業務上ほとんど接点がなかった人、LINEを日常的に使わない人などは、無理に送る必要はありません。むしろ、必要のない相手に送ると、かえって負担や誤解を生むことがあります。
たとえば、業務上でほぼ接することがなかった他部署の人にLINEを送っても、相手にとっては不要なメッセージとなってしまいます。相手に返信するか迷わせる手間をかけることになりかねません。
無理に送ると「なぜ自分に?」と感じさせる可能性もあります。関係性を考えながら、必要な相手に絞りましょう。
【シーン別】退職挨拶LINEの例文集4選
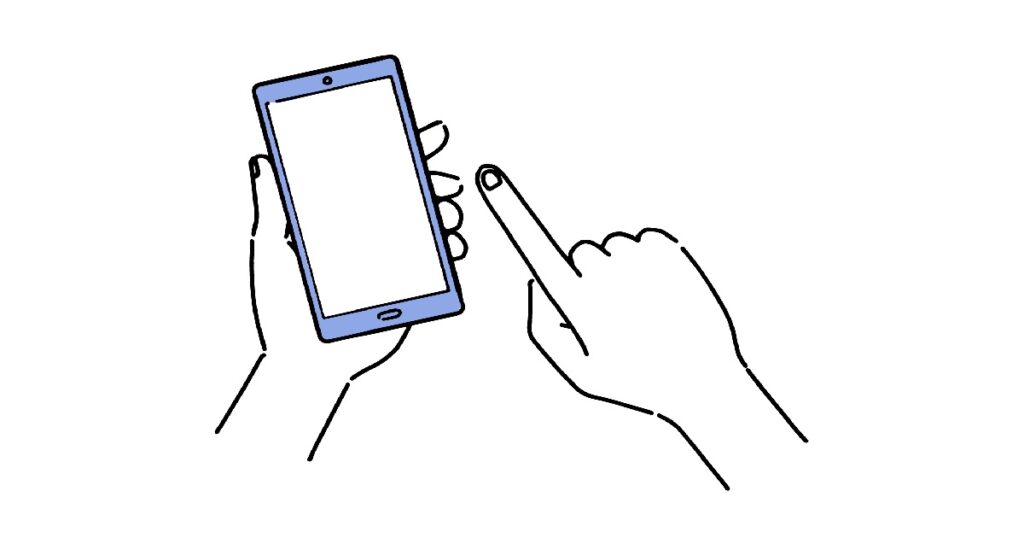
どのような内容で送れば良いか迷う人も多いのではないでしょうか。ここでは、そのまま使える例文をご紹介します。
職場のグループLINEに送る退職挨拶例文
私事ですが、〇月〇日をもって退職することになりました。
これまで支えていただき、本当に感謝しています。
またどこかでご一緒できるのを楽しみにしています。
ポイント
全員に向けた挨拶のため、敬語とフランクさのバランスを意識する
上司・先輩・社長に個別で送る退職挨拶LINE例文
お疲れ様です。〇月〇日をもって退職することになりました。
本来なら直接ご挨拶すべきところ、LINEでのご連絡となりましたことをご容赦ください。
これまでご指導をいただいたこと、心より感謝しております。
今後も学ばせていただいたことを活かして仕事に励みます。
ポイント
直接挨拶ができなかったお詫びを添えると誠実な印象になる
同僚・同期に送るカジュアルな退職挨拶LINE例文
〇月〇日に退職することになりました。
これまで一緒に働けて楽しかったです。
また機会があれば、ご飯に行こうね!
ポイント
普段の距離感に合わせて、ラフな言葉でも問題ない
退職後に送る場合の退職挨拶LINE例文
お世話になっております。
〇月末で退職いたしました。
退職前に直接ご挨拶できず失礼しました。
これまで大変お世話になりました。
今後のご活躍を心よりお祈りしています。
ポイント
相手に誠意が伝わるよう、文章はシンプルにまとめることがポイント
退職挨拶LINEに返信するときのマナー

退職挨拶のLINEを受け取ったとき、返信をしたら良いか、どう返信をすれば良いか悩む人も多いのではないでしょうか。返信の有無や文面のトーンは、相手との関係性や立場によって変わります。ここでは考え方と例文をご紹介します。
返信が必要なケース・不要なケース
退職挨拶LINEに対して返信が必要かどうかは、相手との関係性やメッセージ内容で判断します。
・返信が必要なケース
上司・先輩、チームメンバーなど、直接関わりがあった人からのメッセージには返信しましょう。「こちらこそお世話になりました」「ご指導ありがとうございました」といった簡単な返信で、礼儀と円満な関係を保てます。
・返信が不要なケース
あまり関わりのなかった人や業務上の接点が少なかった人からのメッセージには、必ずしも返信する必要はありません。無理に返すと相手に負担をかけることがあります。
関わりが深く、メッセージ内容に意味がある場合は返信し、関わりが薄く簡単なリアクションのみの場合は無理に返信しない、との判断が目安です。負担を減らしつつ失礼のない対応ができます。
退職挨拶LINEへの返信例文
退職挨拶LINEへの返信でそのまま使える例文をトーンごとにご紹介します。
シンプル
〇〇さん、お疲れ様でした。
これからも応援しております。
ポイント
短くても気持ちは伝わり、退職挨拶で忙しい相手でも負担になりません。
丁寧
〇〇さん、これまでお世話になりました。
新しい環境でもご活躍をお祈りしています。
ポイント
文章を少し長めにして丁寧さを出すことで、目上の方にも違和感なく送れます。
カジュアル
〇〇さん、退職お疲れさま!
今までありがとう。
またご飯行こうね!
ポイント
同期や仲の良い同僚には、フレンドリーな口調で親近感を出せます。
LINEで退職挨拶するときに失敗しないための3つの注意点
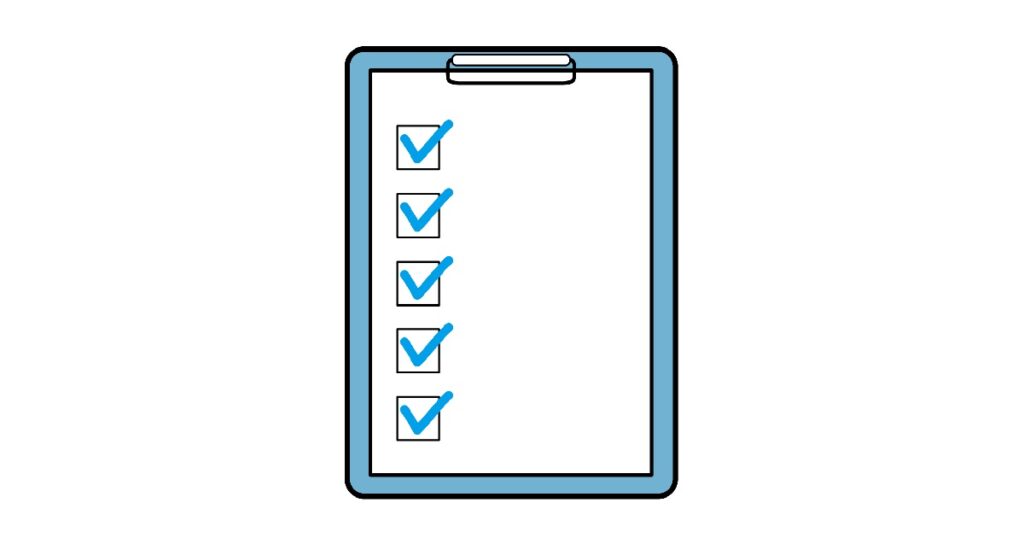
LINEで挨拶をする際には、ちょっとした工夫で印象が大きく変わります。送信前に押さえておきたい注意点や、トラブルを避けるポイントを解説します。
固すぎず・軽すぎない文章の工夫
堅苦しすぎる文章は相手との距離感を生み、軽すぎる文章は誠意が伝わりません。文章が短くても、感謝の気持ちを明確に伝える内容にしましょう。
「お世話になりました」「ありがとうございました」を中心に、適度なフランクさを加えると自然な印象になります。また、文章を一文でまとめず適宜改行を使うと読みやすさが向上します。
たとえば「〇〇さん、これまで本当にお世話になりました。これからも応援しております。」のように、感謝とねぎらいの言葉を分けると印象に残りやすくなります。
相手との関係性に応じたニュアンスの調整がポイントです。
スタンプや絵文字の扱い
スタンプや絵文字や親しみやすさを演出できますが、使い方を間違えると軽く見られることがあります。上司や目上の人には控えめにし、同僚や同期にはラフに使うと自然な印象です。
たとえば、感謝を伝える言葉の最後に控えめなスタンプを添えるだけでも柔らかく近しいイメージになります。複数人のグループLINEでは、目上の人が読む可能性を考え、スタンプは控えめにするのが無難です。
適度に使えば、文章だけより物腰の柔らかい挨拶となります。
誤送信やトラブルを避けるポイント
LINEは手軽なツールですが、操作ミスによる誤送信といったトラブルが発生しやすい点に注意が必要です。送信先を間違えたり、文章に誤字脱字があると関係にヒビが入るリスクがあります。特に複数人に送信する場合やグループLINEでは、誰が読んでも問題ないよう慎重に進めましょう。
送信前に必ず文章を読み返し、送信先を確認しましょう。また、個人情報や業務に関する内部情報はLINEに記載せず、挨拶に留めるようにすると、万が一のときでも安心です。
退職LINEだけで大丈夫?メールや直接挨拶との使い分け
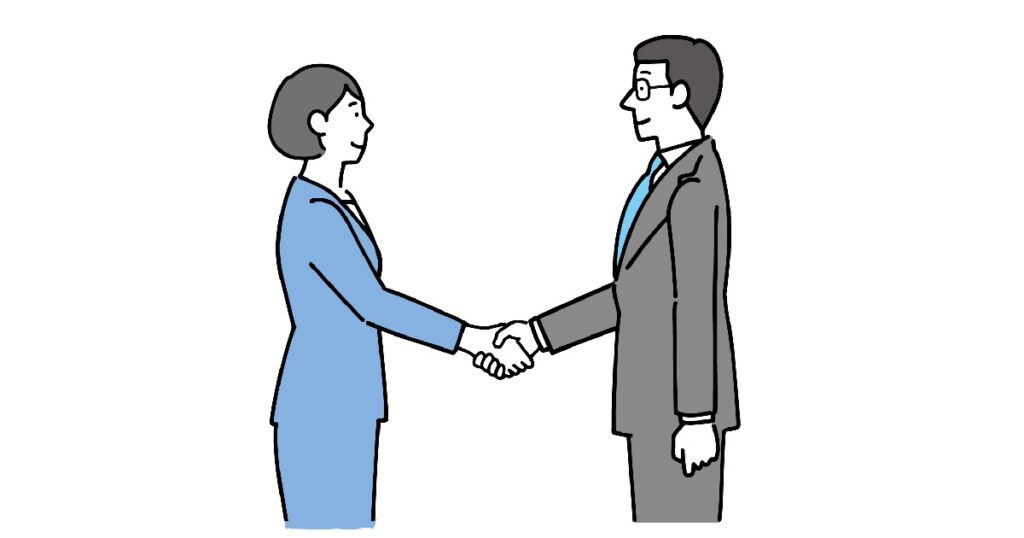
LINEだけで退職挨拶を済ませて良いのか迷う人も多いでしょう。相手や状況によって、LINEだけでは不十分な場合もあります。ここではLINE、メール、直接挨拶の使い分けを解説します。
LINEでは不十分なケース
LINEでの挨拶は手軽ですが、目上の上司や取引先への挨拶には不十分なことがあります。
短い文章がLINEの特徴であるため、誠意が伝わりにくく、思わぬ誤解を受けるリスクがあります。特に、直属の上司や長く関わった先輩には、口頭で挨拶をし、LINEでフォローするのが最適です。
また、会社全体への正式な通知や社外への挨拶もLINEでは失礼だと捉えられることがあります。LINEではなくメールや直接の挨拶で、より礼儀正しい印象を与えられます。
LINEはカジュアルなコミュニケーションツールであるため、立場や状況を考えて使い分けるのがポイントです。
メールとLINEを併用する場面
メールとLINEを組み合わせることで、さらに印象に残る挨拶が可能です。
LINEでカジュアルにグループ全体へ一斉挨拶を送り、個別にお世話になった上司や先輩にはメールで丁寧に送る、といった方法があります。メールでは相手に合わせた挨拶文を書くことで、感謝をより強く伝えられ、相手の印象に残る挨拶になるでしょう。
連絡方法の併用は、LINEの手軽さとメールでの丁寧さが両立でき、相手に配慮が行き届いた印象を与えます。
信頼を損なわない工夫
LINEで退職挨拶を送るときは、簡潔で誠意が伝わる文章や工夫を心掛けましょう。
- 改行を入れて読みやすくする
- 相手の名前を入れて個別感を出す
また最後の一言を変えるだけでも、全体の印象が変わります。「お体に気をつけて」「応援しています」「活躍を期待しています」といった一言を添えると、柔らかい印象になります。相手を気にかける姿勢を伝えられ好印象です。
工夫次第で、LINEでも信頼を損なわず円満に退職できるでしょう。円満に退職する流れについては、こちらの記事もご覧ください。
LINEでの退職挨拶のよくある疑問Q&A
LINEでの退職挨拶でよくある質問をまとめました。
- タイミングがあわず上司の1人だけ退職の挨拶ができない……LINEでの挨拶で良い?
-
直接会えない場合はLINEで問題ありません。ただし、文章は簡潔で誠意を感じさせる内容にし、直接挨拶ができない旨の謝罪も添えましょう。
- 退職の挨拶を直接・チャットでした場合は、LINEでの挨拶は不要?
-
直接挨拶した後でも、LINEで軽くフォローすると印象が良くなることもあります。「改めてお世話になりました」と一言添える程度で十分です。
- 有給消化して退職する場合、いつLINEで挨拶すれば良い?
-
有給消化する場合は、最終出勤日に送るのが一般的です。事前にスケジュールを確認し、相手別に送信するタイミングを調整すると安心できます。
まとめ
この記事では、LINEでの退職挨拶について解説しました。
LINEでの退職挨拶は、便利で手軽な反面、送る相手や文章のトーンを誤ると印象を損ねる可能性があります。基本マナーやタイミング、シーン別例文を参考にして、相手に誠意が伝わる挨拶を送るようにしましょう。
退職の挨拶は、最後の印象を左右する貴重な機会で、今後の関係にも影響します。LINEを上手に活用して、円満に退職しましょう。