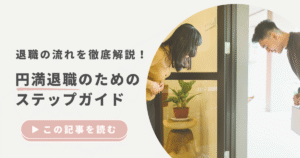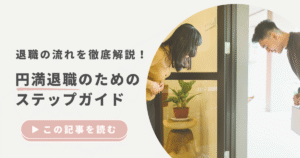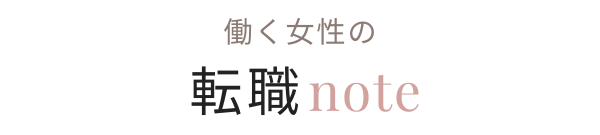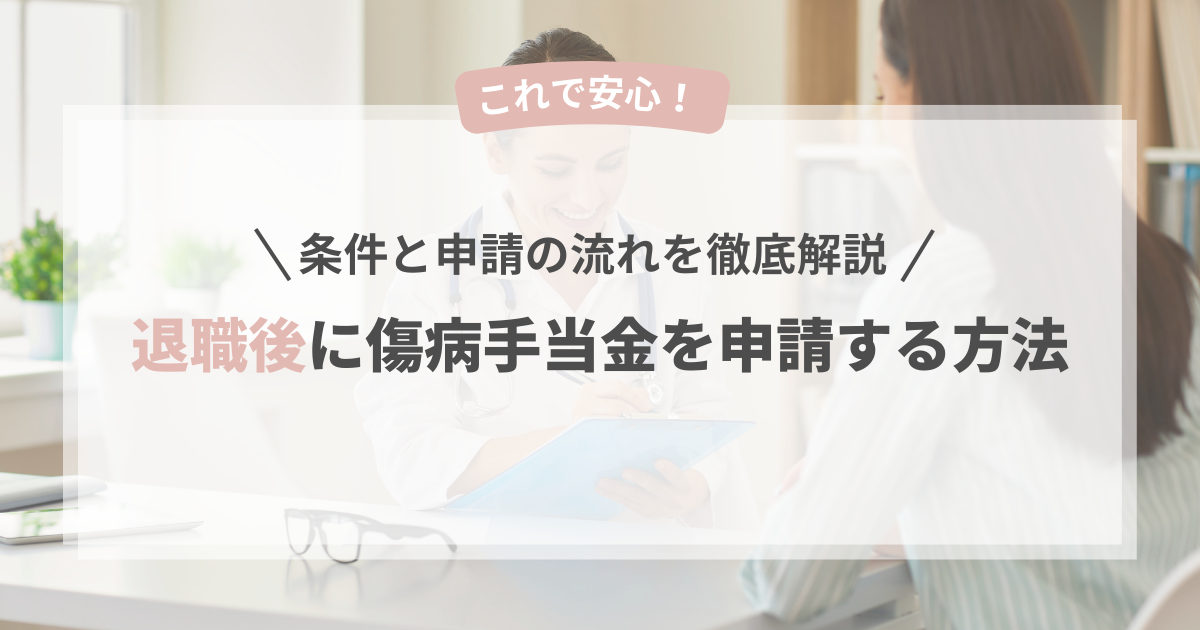- 退職後に受け取るための条件
- 傷病手当金の支給期間と申請期限
- 退職後に初めて傷病手当金を申請する方法
傷病手当金は、病気やケガで働けないときに生活を支えてくれる制度です。
体調を崩し仕事が続けられず退職を検討している方の中には、退職後の生活に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

退職したけど体調不良で働けない……退職後でも受給できる?



無事に受給できるか不安……退職後でも受給できる条件は?



申請する方法がわからない……
実は、受給条件を満たしていれば、退職後に初めて申請した場合でも傷病手当金は支給されます。
この記事では、退職後に初めて傷病手当金を申請される方向けに、申請する方法や注意点をわかりやすく解説します。
最後まで読めば、申請する方法がわかり、安心して療養ができるでしょう。
本記事のライター:伊藤えま
採用・人事歴10年以上。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)取得済み。採用統括責任者として現場で得てきたリアルな知見を、発信している。
傷病手当金とは?退職後でも受給できる?


傷病手当金とはどのような給付金なのか、また退職後でも受給できるのかを解説します。
傷病手当金とは
傷病手当金とは病気やケガで仕事ができず、事業主から十分な給与が受けられない場合、支給される給付金です。
加入している(退職済の場合には加入していた)健康保険組合や協会けんぽから支給されます。
傷病手当金は退職後でも受給できる?
傷病手当金は退職後でも受給ができます。また、退職後に初めて申請しても、支給条件を満たしていれば受給可能です。
下記のような場合でも、条件を満たしていれば受給対象になります。
- 在職中は有給休暇を使用し、退職後に初めて申請するケース
- 発症から退職までの期間が短いケース
退職後に傷病手当金を受け取るための条件


退職後に傷病手当金を受給するには条件を満たす必要があります。
ひとつずつ詳しく解説します。
業務外での病気やケガの療養のための休業であること
業務中や通勤中の病気やケガは、労災保険の対象です。一方、傷病手当金は「業務外」での病気やケガでの休業を対象としています。そのため、傷病手当金は「業務外」での病気やケガである必要があります。
仕事に就くことができないこと
「仕事に就くことができない」の判断は、医師の意見を参考にしつつ、最終的には健康保険組合や協会が行います。自己判断は認められないことに注意しましょう。
また、医師が「仕事に就くことができない」と判断する期間は、初診日以降の期間です。初診日より前の期間については、欠勤をしていたとしても「仕事に就くことができない」と医師が判断できないからです。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
仕事を休んだ連続した3日間を「待機」として、4日目以降の仕事を休んだ日を対象に支給されます。
「待機」は、有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれます。
画像出典:病気やケガで会社を休んだとき|全国健康保険協会
被保険者期間が退職日までに継続して1年以上あること
退職日までに1年以上継続して健康保険に加入していることが必要です。
退職後に任意継続被保険者や国民健康保険の被保険者となった場合でも、受給できます。
退職日に傷病手当金を受けている、もしくは受けられる状態であること
退職日にあいさつや荷物整理などで出勤すると「仕事に就くことができない」と見なされず、退職後の傷病手当金は受け取れなくなる可能性があります。
退職後も受給する場合には、退職日に受給している、もしくは受給を受けられる状態であることが必要です。
「退職後に傷病手当金の継続給付を希望している」と職場に相談すると、退職日の過ごし方について調整してもらえることもあります。
傷病手当金の支給期間と申請期限


傷病手当金には、支給される期間と申請できる期限が設けられています。
傷病手当金の支給期間
傷病手当金は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月間支給されます。
ただし、退職後に受給している場合、一度「仕事に就くことができる状態」となり、その後さらに「仕事に就くことができない状態」になっても、傷病手当金は再開できません。退職後の傷病手当金は継続給付が条件です。支給期間が残っている場合でも、1日でも「仕事に就くことができる状態」となった場合には、以降の期間は傷病手当金は支給されません。
傷病手当金はいつまでに申請したら良い?
退職後であっても、労務不能だった日から2年以内であれば申請が可能です。
傷病手当金には時効があります。1日単位で給付金が支払われるため、時効も1日単位となり、労務不能であった日ごとにその翌日から2年が請求できる期間です。
例:
| 労務不能だった日 | 時効の起算日 | 請求できる期間 |
|---|---|---|
| 2025年8月1日 | 2025年8月2日 | 2027年8月1日まで |
| 2025年9月12日 | 2025年9月13日 | 2027年9月12日まで |
傷病手当金の支給金額ともらえない・減額されるケース


支給金額は、支給開始日以前の標準月額を基準として計算されます。しかしながら、他の公的な給付金を受けている場合は、減額される可能性があります。
傷病手当金の支給金額
傷病手当金は1日あたりで支給され、支給金額は下記の計算式で計算します。
1日あたりの給与のおよそ3分の2が支給されると考えてよいでしょう。
傷病手当金がもらえない・減額されるケース
他の公的な給付金を受けている場合は、傷病手当金がもらえない、もしくは減額されることがあります。
具体的には下記のようなケースです。
- 傷病手当金と出産手当金がもらえる時
- 退職後に老齢(退職)年金がもらえる時
- 障害厚生年金または障害手当金がもらえる時
- 労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)時
退職後に初めて傷病手当金を申請する方法


在職中は有給消化をして、退職後に傷病手当金を申請する方も多いのではないでしょうか。ここでは、退職後に初めて傷病手当金を申請する方法について、詳しく解説します。
申請に必要な書類
傷病手当金申請書が必要で、加入していた健康保険組合や協会により多少の違いはありますが、たいていは以下の構成となっています。
- 被保険者記入用(あなたが記入する箇所)
- 事業主記入用(会社が記入する箇所)
- 療養担当者記入用(医師が記入する箇所)
>> 協会けんぽの傷病手当金申請書はこちらから(全国健康保険協会ホームページ)
下記の場合には、申請するときに追加で書類が必要です。
- 申請書にマイナンバーを記入する場合
本人確認書類(健康保険組合や協会による)
- 障害年金や老齢年金など、他の公的な給付金を受けている場合
それらの受給額がわかる書類
- 支給開始以前の12ヶ月以内で転職した人や健康保険の資格に変更があった人
以前の事業所の名称、所在地および事業所に使用されていた期間がわかる書類
- 傷病の原因が第三者の行為による場合
第三者行為による傷病届
申請先
申請先は退職前に加入していた健康保険協会、もしくは健康保険組合です。退職後の申請は会社を経由せず、必要書類を自分で集め、自分で申請をします。
申請の流れ
退職してから初めて傷病手当金を申請する時は、在職した期間から申請をします。具体的な申請の流れを解説します。
傷病手当金の支給条件を満たしているか確認しましょう。
退職日の前日までに3日間連続した「待機」が完成していて、退職日当日も出勤していないことが重要です。退職日当日が、有給休暇でも問題ありません。
退職後に申請書を入手するには、下記のような方法があります。
- 以前勤務していた会社から入手する
- 加入していた健康保険組合や協会けんぽのホームページからダウンロードする
- 加入していた健康保険組合や協会けんぽに直接連絡して郵送してもらう
医師に申請書の「療養担当者の欄」に記入をしてもらいましょう。医師が記入する欄には、「労務不能と認めた期間」や「傷病名」「発病日」などの項目があります。
労務不能と認めた期間について、医師は過去の期間しか記入できません。なぜなら、未来の期間まで労務不能かどうかを判断できないからです。
そのため、傷病手当金は仕事ができなかった期間をさかのぼって申請します。たとえば、8月31日までの申請をするなら、9月以降に医師に記入を依頼する必要があります。
また、記入を依頼してから受け取るまで、数週間かかる場合も珍しくありません。スケジュールは余裕をもって進めましょう。
申請書の「本人記入欄」を記入します。
医師が記入する「療養担当者の欄」と自分が記入する欄には重複する項目があります。そのため、病院で申請書を受け取ってから、自分で記入するのがおすすめです。医師が記入した内容を確認しながら書くことで、誤りなくスムーズに申請できます。
申請期間(労務不能と認めた期間)に在職していた期間を含む場合には、以前の会社に「事業主記入用」への記入を依頼する必要があります。
会社に申請書を提出して記入してもらいましょう。郵送する際には、返信用封筒も同封すると会社側に負担をかけづらくなります。スムーズなやり取りのために、丁寧な対応を心がけましょう。
会社が記入する「事業主記入用」が手元に届いたら、健康保険組合や協会けんぽへ申請します。送付する場合は、送付先を確認してから送付すると安心です。
すべての書類が揃った申請書が健康保険組合や協会けんぽへ届くと、支給審査が開始されます。
審査が完了後、通知書が手元に届き支給決定となれば、指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後に傷病手当金を申請・受給するときの4つの注意点


退職後に傷病手当金を申請・受給するときは注意する点があります。
受給できるまでに日数がかかる
健康保険組合や協会けんぽにより違いはありますが、初めて申請した時には通知書が届くまで1〜2ヶ月ほどかかる場合があります。初回の申請は審査に時間がかかるからです。
傷病手当金を受給できるまでの生活費は、確保しておくと安心です。
失業保険と併用はできない
傷病手当金と失業保険は併用ができません。
傷病手当金は「仕事に就くことができないこと」が前提ですが、失業保険は「働けること」が前提です。前提とする条件が異なるため、両方の条件を同じ期間に満たすことはありえないからです。
それぞれを順番に受け取ることは可能です。療養期間中は傷病手当金を受給し、働けるようになったら失業保険を受給します。
ただし、失業保険の受給期間は退職日の翌日から1年間のため、療養期間中に受給期間が終わる可能性があります。療養期間中に、失業保険の受給期間を延長する手続きをハローワークで行うことで、最長3年に延長できます。
通院は医師の指示に従い最低でも月に1度は病院を受診する
通院は医師の指示に従って、少なくとも月に1度は受診するようにしましょう。
医師の指示を守らず通院をしなかったりした場合、「就業不可と判断できない期間」として申請書を記入してもらえないリスクがあります。
退職後の傷病手当金は、継続給付が条件です。就業不可と判断できない期間があり、就業不可の期間が途切れると、傷病手当金は受給できなくなります。
受給金額により家族の扶養に入れないことがある
傷病手当金の受給金額によっては、家族の扶養に入れない場合があります。
家族の扶養に入るには収入の上限があり、傷病手当金は社会保険の扶養認定における「収入」に含まれるからです。
一方、税法上の扶養における「所得」には含まれないため、非課税所得となり、所得税はかかりません。
扶養の基準は健康保険組合や協会けんぽにより異なるため、家族が加入している健康保険に直接問い合わせるのが最も確実です。
退職後に初めて傷病手当金を申請した人の体験談
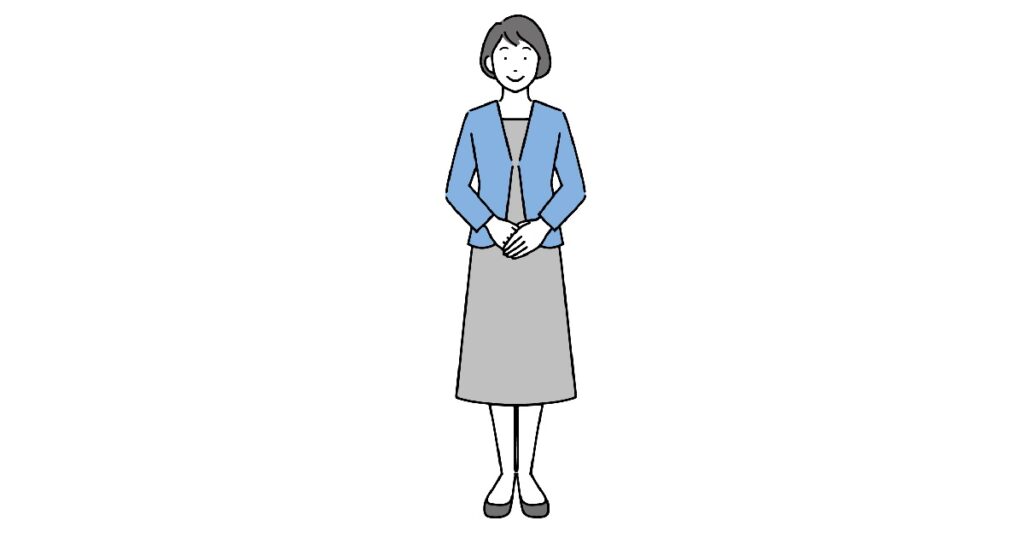
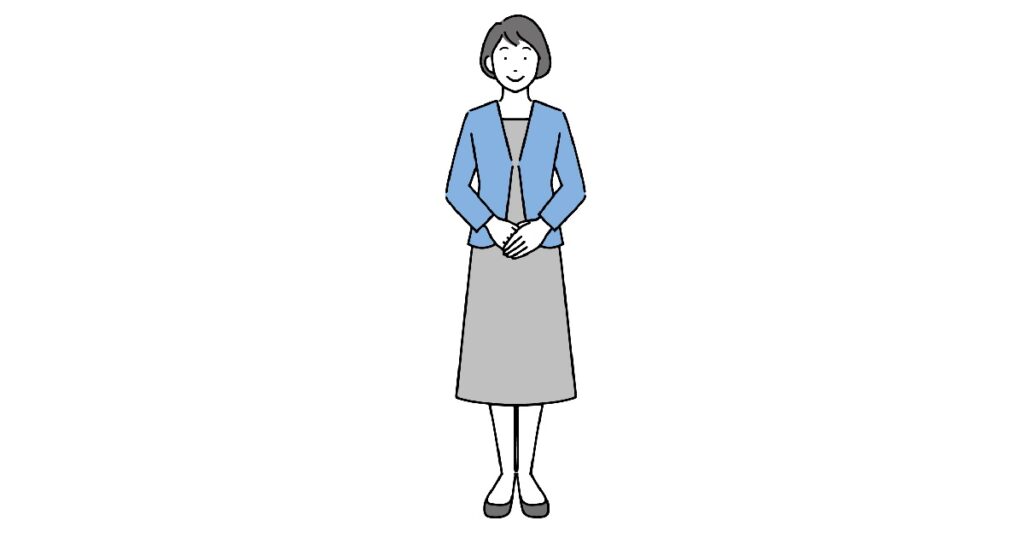
体験談:40代 女性 事務職
在職中に体調を崩し、医師から「長期の休養が必要」と診断されました。今後の生活に不安を感じる中、傷病手当金を医師から知ったのが、退職後の申請を考えるきっかけでした。
長期療養のため退職を決意し、有給休暇を消化して退職する流れに。有給休暇中に傷病手当金の手続き方法や必要書類を確認しておきました。
退職後、医師と会社に必要書類の記入を依頼し、無事に自分で申請。申請から10日ほどで通知書が届きました。
体調が優れない中、すべて自分で調べるのは大変でしたが、事前に手続きの流れを把握しておいたことでスムーズに進められました。特に、退職前に会社へ傷病手当金の申請をする予定を伝えておいたことが、その後のやり取りを円滑にする上で重要だったと感じています。
よくある質問
傷病手当金についてよくある質問をまとめました。
- 退職後に国保に切り替えても傷病手当金は受給できる?
-
退職後に国民健康保険の被保険者となった場合でも、傷病手当金は受給できます。傷病手当金は退職前に加入していた健康保険組合や協会けんぽに申請をします。
- 傷病手当金を受給していたことは転職先にバレる?
-
転職先で同一の傷病により、再度、傷病手当金を申請するとバレることがあります。
同一の傷病についての傷病手当金は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月間受給ができます。前回の傷病手当金の受給から1年程度の期間が空いていない場合には、同一の傷病とみなされることが多く、支給期間が通算され、受給期間が短くなるからです。
- 再就職やアルバイトを始めたら傷病手当金はどうなる?
-
再就職やアルバイトを始めたら、傷病手当金は原則として支給停止になります。傷病手当金は「働くことができないこと」が条件だからです。
- 傷病手当金を申請後、通知書はどれぐらいで届く?
-
加入していた健康保険の団体により大きく異なります。特に初回は時間がかかることも多く、1〜2ヶ月程度かかるケースもあります。
- 傷病手当金の申請代行サービスは利用した方が良い?
-
自分で調べて自分で申請も可能です。ただ体調を崩している中、自分ですべて進めるのは難しい場合もあるかもしれません。そのような時は申請代行サービスも選択肢として検討してもよいでしょう。
まとめ
この記事では、退職後の傷病手当金について解説しました。
傷病手当金は、病気やけがで仕事に就けない時に療養に専念するための支援制度です。体調が回復しないまま無理をして転職活動を始めてしまうと、病気が再発・悪化するおそれもあります。
まずはしっかり休養して、回復を最優先にしましょう。
そのためにも、傷病手当金の制度を正しく理解し、自分の権利として活用してください。