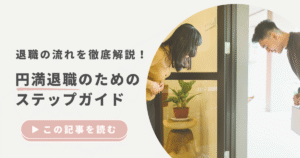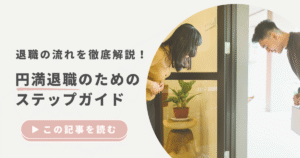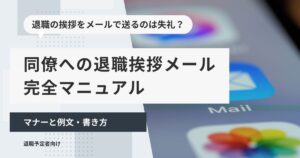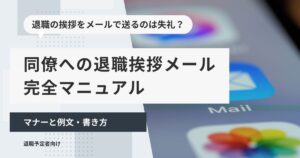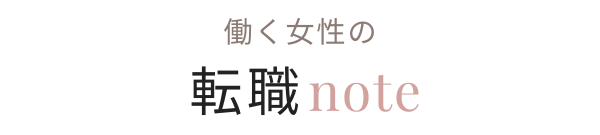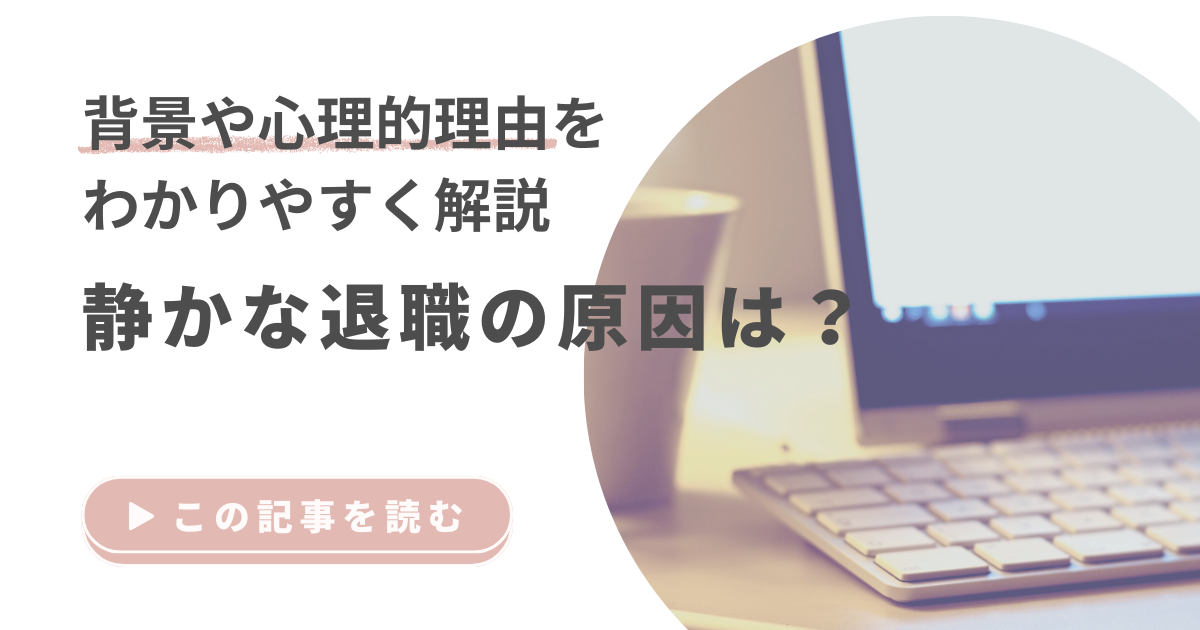- 静かな退職とは?Quiet Quittingの違い
- 静かな退職の原因は?よくある理由と背景
- 静かな退職を選ぶ人の心理的理由
- 静かな退職の兆候チェックリスト

最近『静かな退職』と聞くけれど、実際にどんな状態なの?



仕事に不満があるわけではないのに、どこか気持ちが冷めている……
そんなモヤモヤを感じている方も多いのではないでしょうか。
静かな退職とは、実際に退職しているのではなく、気持ちで退職している状態のことです。
この記事では、静かな退職に繋がる原因や背景、心理的理由について、採用・人事のプロがわかりやすく解説します。
本記事のライター:伊藤えま
採用・人事歴10年以上。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)取得済み。
採用統括責任者として現場で得てきたリアルな知見を、発信している。
自分の働き方を見直すヒントにしてみてください。
静かな退職とは?意味とQuiet Quittingの違い


静かな退職とは、現実で退職するのではなく、在籍しながら必要最低限の仕事だけをしている状態のことです。
仕事や会社に対して持つ熱意や意欲であるエンゲージメントの低下が原因としてあげられます。
2022年にTikTokでアメリカのキャリアコーチが主張した「Quiet Quitting」がはじまりとされています。
Quiet Quittingを和訳した言葉が「静かな退職」です。
一日中働く「ハッスルカルチャー」の対義語のような位置づけとして使われます。
静かな退職の特徴


静かな退職には、働き方に特徴があります。
必要最低限の業務しかしない
指示された業務以外はやりません。
プラスαの仕事はしないので、自ら提案することもありません。
また、残業も少なくなります。
不満そうに見えない
周りに愚痴や不満は言わないので、不満があるようには見えづらいのも特徴です。
ただ淡々と事務的に業務を進めます。
キャリアの成長を目指さない
スキルアップに繋がる取り組みを避け、キャリアの成長は目指しません。
職場からの評価には、興味が持てない状況です。
日本における静かな退職の現状


働いている理由について、日本の若年層ではキャリアアップのためではなく、お金を理由としている人が多い傾向です。
厚生労働省の「令和5年若年者雇用実態調査」によると、若年層の働いている理由について、下記3つが順に多い結果となりました。
- 主たる稼ぎ手として生活を維持するため 51%
- 自分の学費や娯楽費を稼ぐため 49.7%
- 自立のため 31.5%
スキルアップや達成感を目的とした理由を選ぶ人は少なくなっています。
- 生きがい・社会参加のため 21.6%
- 自己実現のため 16.7%
- 将来のための技能・技術の習得のため 18.4%
若年労働者:
満 15~34 歳の労働者
「令和5年若年者雇用実態調査」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-r05_06.pdf)を加工して作成
静かな退職の主な原因|よくある理由と背景
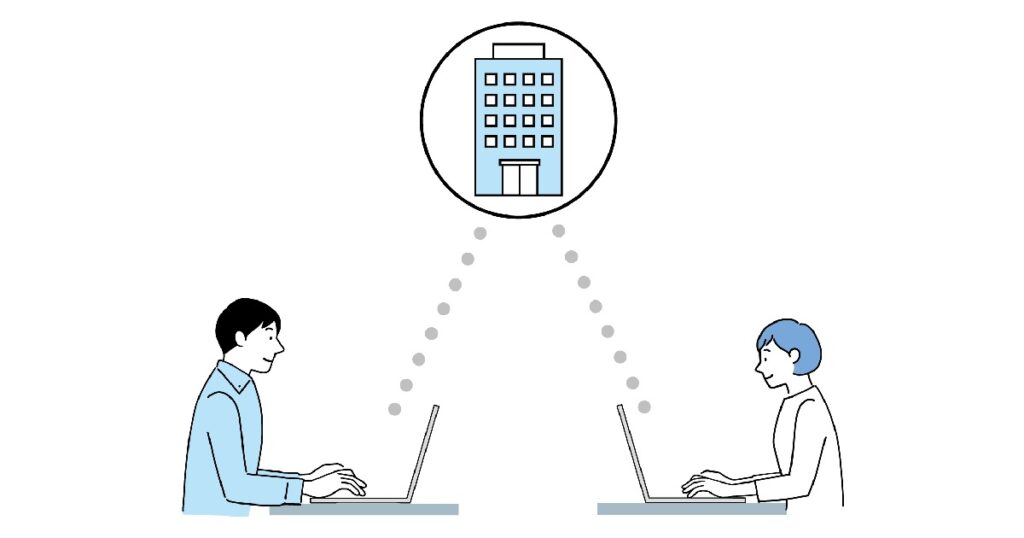
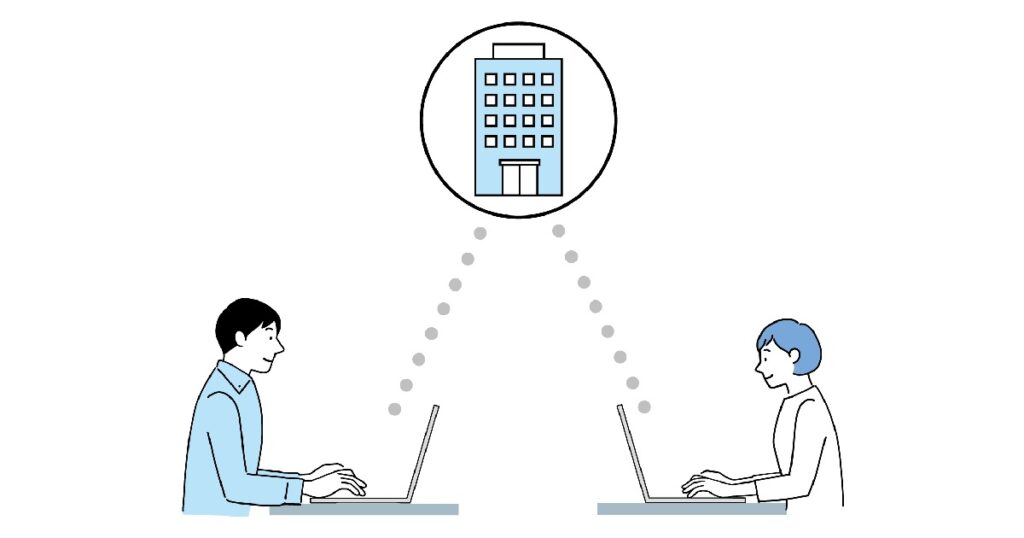
静かな退職の主な原因を、背景とあわせて見ていきましょう。
働き方の多様化
働き方が多様化していることが原因のひとつです。
多様化した結果、コミュニケーションが難しく不足している場面が多くなり、結果として、上司と同僚と信頼関係が築きにくい環境になっています。
働き方改革やコロナ禍を経たことで、リモートワークや時短勤務制度など多様な働き方が広がりました。
顔を直接あわせる機会が減ったことによるコミュニケーション不足が課題となっています。
働きやすい環境を整えたことが、静かな退職に繋がる要因となっています。
ワークライフバランスの重視
ワークライフバランスを重視する考え方が浸透したこともきっかけです。
私生活の充実も大切と考える人が増え、仕事だけでなく自分の時間も大切にできる働き方を希望する人が増えました。
かつての日本は「長い時間働いているほど偉い」という風潮がありました。
しかしながら、近年は終身雇用制度の崩壊によって、企業に貢献しても評価がされづらくなっています。
そこで社員は仕事とプライベートを両立させるワークライフバランスを求めるようになりました。
ロールモデルがいない
職場に目標になるロールモデルがいないことも原因です。
目指す方向が定まらず、日々の業務へのモチベーション維持が難しくなります。
マネジメントに疲れた管理職を見て、キャリアアップに希望が持てなくなっています。
静かな退職を選ぶ人の心理的理由
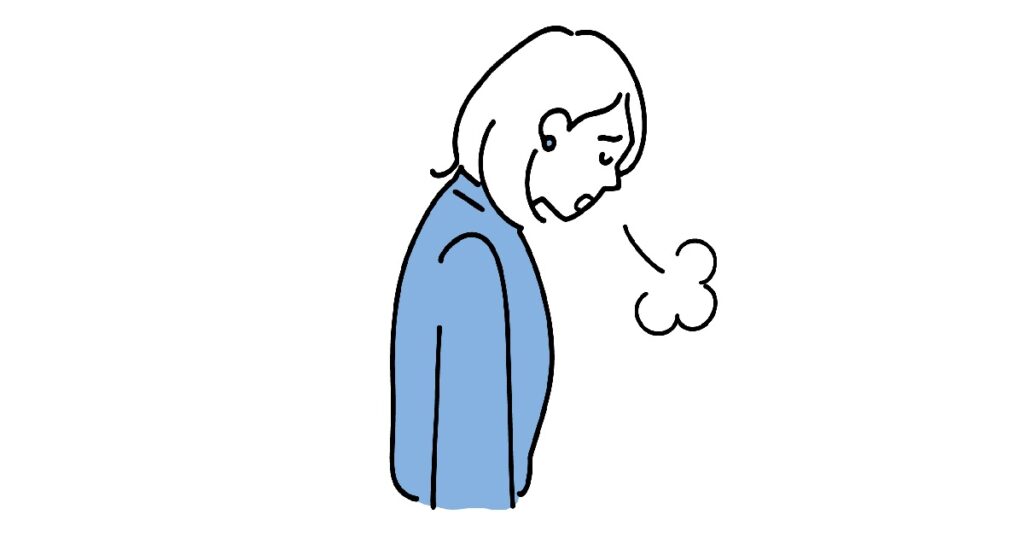
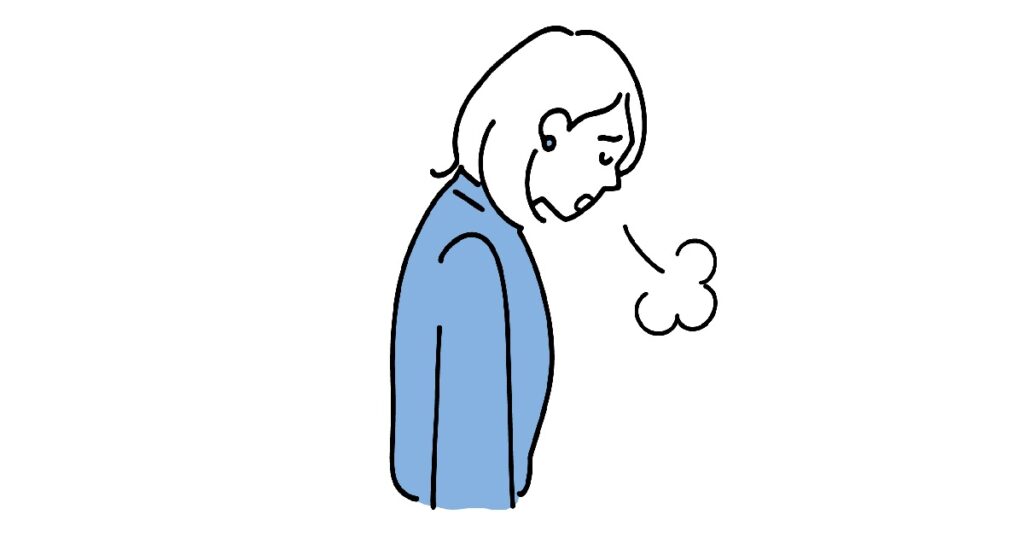
静かな退職を選ぶ人には心理的な理由があります。
努力しても評価されないと感じている
努力しても公平な評価がされないことで、モチベーションが上がらなくなります。
年功序列や入社順での評価をしている環境では、正当な評価がなされているとは言えません。
仕事を人生の主軸にしたくない
働き方改革やコロナ禍をきっかけに「仕事だけに時間を使いたくない」という考え方が広まりました。
仕事以外の時間を自分のために有効活用する意識が浸透しています。
改善されないと諦めている
提案しても受け入れられない環境では、人は静かに会社と距離を置きます。
効率化を目的とした業務フローの改善を提案しても「新しいやり方を覚えるのが面倒」と却下されることもあるかもしれません。
すると、意見を受け入れてもらえないと見切りをつけるようになります。
無理したくない
無理をして身体を壊すリスクを防いでいる場合もあります。
手を抜いているのではなく、自分を守る手段として選んでいるケースもあるでしょう。
企業側も評価制度やコミュニケーションの見直しが必要です。
静かな退職の兆候・サイン|セルフチェックリスト
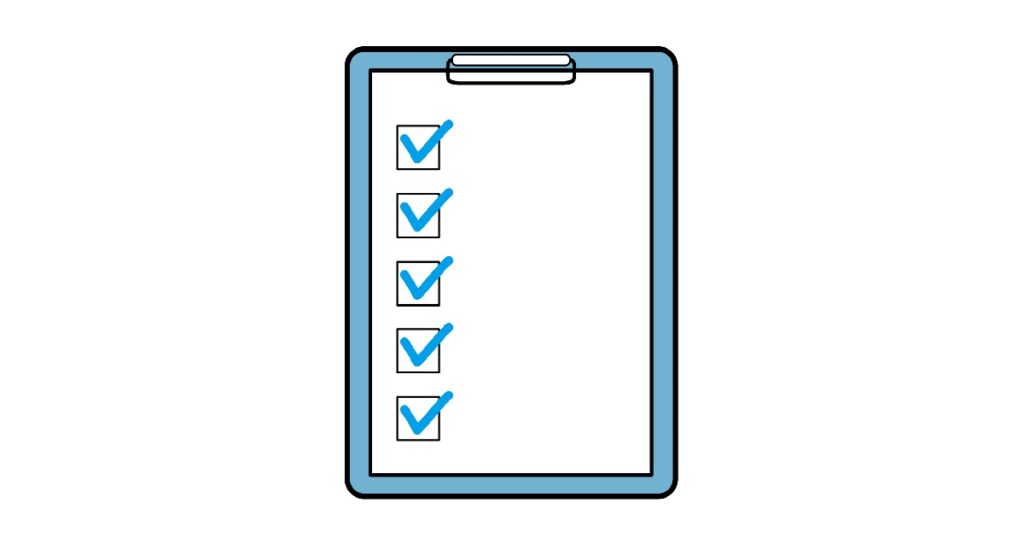
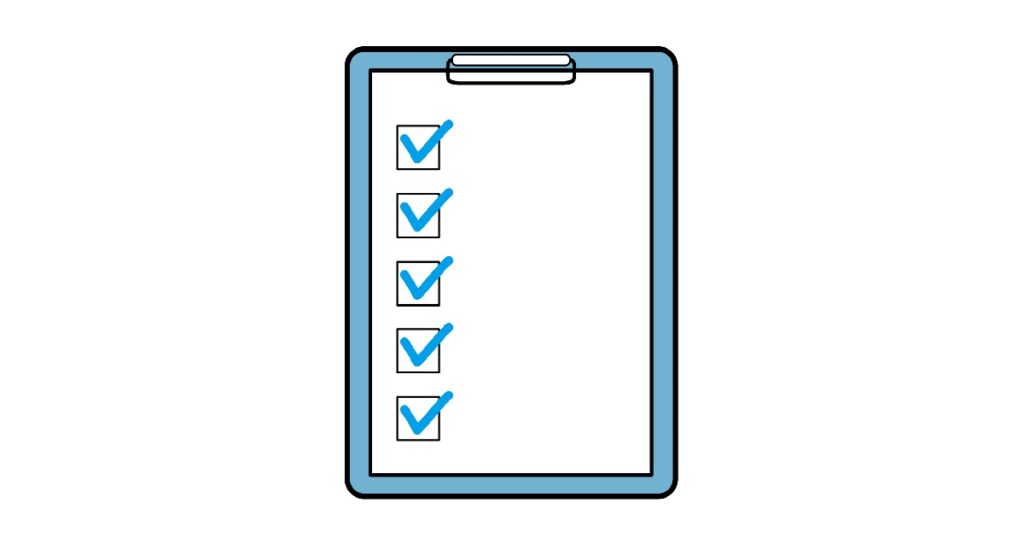
静かな退職をしている人には兆候があります。
- 無難な仕事しかしない
- 積極性がなくなる
- 必要最低限のコミュニケーションしかしない
- 存在感が薄くなる
- 残業を急にしなくなる
- 仕事のスケジュールに構わず残業をすべて消化する
- スキルアップや評価に関心がなくなる
兆候が当てはまる場合は、一度上司や人事に相談してみるのも一つの方法です。
静かな退職とサイレント退職の違いは?


「静かな退職」と「サイレント退職」は、どちらとも“Quiet Quitting”から派生している言葉です。
混同する人も多いですが、実は使われ方に違いがあります。
- 静かな退職
退職はせず、在籍しながら必要最低限の仕事だけをしている状態です。
物理的に辞めるのではなく「心の中で辞めている状態」を意味します。
- サイレント退職
辞める兆候を見せずに、突然退職することです。
不満や悩みを相談せず退職を決断するため、周囲からは唐突に退職するように感じられます。
静かな退職に関するよくある質問
- 静かな退職をしていると解雇されることがある?
-
職場での評価が低いことから、解雇される対象者になることがあります。
正社員であれば、企業は簡単には解雇できないよう定められています。
しかしながら、業績不振で人員削減をせざるを得ない場合では、対象者として選ばれる可能性があります。
- 静かな退職は何が悪いの?
-
最低限の品質で業務を行っていれば職務は果たしているので、一概に悪いとは言えません。
積極的な姿勢が見られないとしても、周りに迷惑をかけるとは限りません。
ただ、成長機会が減りやすく、将来的にキャリアの選択肢が狭まる可能性は理解しておきましょう。
まとめ
この記事では、静かな退職について解説しました。
ワークライフバランスを重視する考え方が広まったことなどにより、静かな退職を選ぶ人は増加傾向です。
静かな退職は誰にでも起こり得るものです。
兆候に気づいたら、信頼できる上司や人事に相談するなど、まずは小さな一歩を踏み出してみましょう。