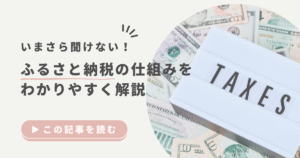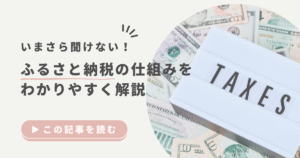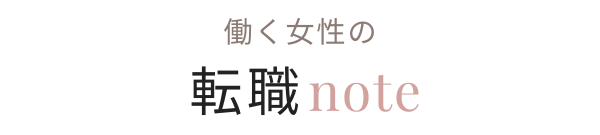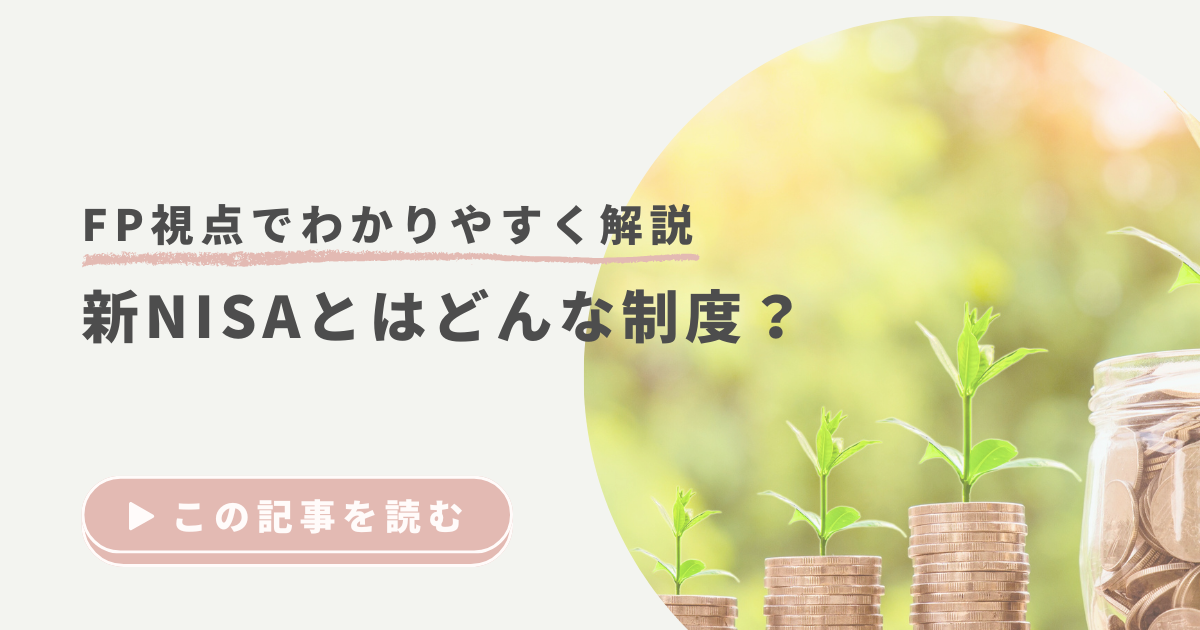2024年に新NISAが開始されてから、いままでより使いやすくなり、柔軟に資産形成がしやすくなりました。NISAについて興味はあるけど、難しそうと思われている方も多いのではないでしょうか。

NISAは難しそう……
NISAとは、投資で得た運用益に税金がかからなくなる制度です。
この記事では、NISA(新NISA)の仕組みやどんな方に向いているのかをわかりやすく解説します。
将来に向けた資産形成の方法を考えている方は、ぜひ参考にしてください。


- 採用・人事歴10年以上
- 中途採用で900名以上を選考
- 採用統括責任者として書類選考・面接・採否の決定を担当
- 人事評価基準の策定・人事考課にも従事
- 社員のキャリア相談を多数経験
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)
NISAとは?
NISAとは投資で得た運用益(譲渡益や配当)に税金がかからなくなる制度です。少額投資非課税制度といいます。
通常、投資で得た運用益には、20.315%の税金がかかります。NISAを利用して投資をすれば運用益に税金がかからず非課税のため、運用益がそのまま手元に残ります。
例:
100万円投資して10万円の利益が出た場合
→通常は利益に税金がかかり、手元に約8万円しか残らない
→NISAを利用した場合には、手元にそのまま10万円が残る
新NISAの導入により制度がさらに使いやすくなったので、多くの人にとって魅力的な選択肢となっています。
出典:政府広報オンライン「「NISA」って何?わかりやすく解説」
新NISAのポイント
新NISAには、以下のようなポイントがあります。
- 1人1口座
NISA口座は、日本国内に住む18歳以上の人が対象で、1人につき1口座のみ開設できます。
- 生涯非課税限度額は1,800万円まで
旧NISAの生涯非課税限度額は最大800万円まででしたが、新NISAは1,800万円まで(うち成長投資枠は1,200万円まで)拡大されました。売却すると、その枠は翌年以降に再度利用が可能です。
NISA(新NISA)のメリット・デメリット
NISA制度(新NISA)はメリットもありますが、デメリットもあります。
メリット
- 運用益が非課税になる期間が無期限に
旧NISAでは税金がかからない期間が最大20年でしたが、新NISAでは無期限となりました。
いままでは非課税のメリットを受けるためには20年以内に売却をする必要がありました。新NISAではライフプランにあわせて長期的に運用を続けることが可能なので、20年以上の運用を検討している方には大きなメリットです。
- 少額で投資が始められる
少ない金額で投資が始められるので、投資初心者でも始めやすいのが特徴です。
投資というと大きい金額を一括で投資するイメージがあるのではないでしょうか。NISAの「つみたて投資枠」では、あらかじめ決めた金額を定期的に積み立てることで投資が可能です。つみたて投資ができる金額は金融機関により異なりますが、月額100円からつみたてが可能な金融機関もあります。
- いつでも売却可能
NISA制度ではいつでも売却できるのはメリットです。住宅購入や進学のための学費など、大きな出費が必要になるタイミングにあわせて売却して現金化できます。
- NISAでは原則確定申告が不要
原則としてNISAでは、確定申告が不要です。確定申告は、所得金額に対する所得税の金額を計算して確定する手続きです。NISAでは運用益には税金はかからないため、確定申告の手続きが不要です。
ただし、下記のケースでは確定申告が必要となることがあります。
- 配当金の受け取り方法が「株式数比例配分方式」以外の場合
- 旧NISAを非課税保有期間終了後に課税口座に払い出しされた場合
デメリット
- 元本割れのリスク
NISAは投資のため元本保証はなく、元本割れする可能性があります。つみたて投資枠で、長い期間積み立てを続けることで元本割れのリスクを小さくすることができます。
- 利益がでていないと非課税のメリットは受けられない
NISAは利益がでていない場合には、非課税のメリットを受けることはできません。運用益に税金がかからない制度のため、メリットがあるのは運用益がでている場合です。
- 購入できる商品が限られている
NISAの投資対象商品は限られていて、金融機関や、成長投資枠とつみたて投資枠で対象商品が異なります。投資したい商品があるかどうかで金融機関を選ぶことも重要です。
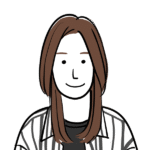
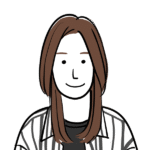
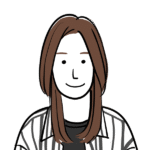
メリットだけではなく、デメリットも把握しておきましょう!
NISAとiDeCoの違い
NISAと同じく税制優遇がある制度としてiDeCoがあります。iDeCoは「個人型確定拠出年金」で、老後資金を自分で積み立てる「私的年金」です。ここではNISAとiDeCoの違いについて解説します。
- iDeCoは60歳まで引き出すことができない
iDeCoは原則60歳になるまで引き出すことができません。iDeCoは老後の資産形成を目的としているための制度だからです。
NISAは引き出すタイミングを自由に決めることができます。
- iDeCoの掛金は所得控除の対象
iDeCoは運用益に加えて、毎月積み立てる掛金の全額が所得控除の対象となります。所得控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽減される効果があります。
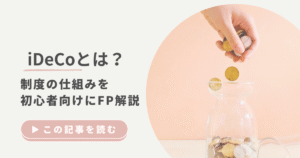
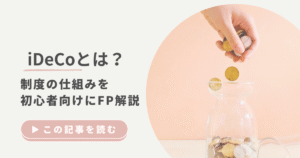
NISAが向いている方
NISAは以下のような方におすすめです。
- 少額で長期的にコツコツと資産運用をしたい
- 将来の大きな出費に備えたい
- 当面使う予定がないお金がある
はじめての方におすすめ「つみたて投資枠」
投資がはじめての方におすすめなのは「つみたて投資枠」です。
つみたて投資枠は長期の積み立て・分散投資に適した一定の投資信託が対象です。長期間の積み立てに適している商品なので、日々の値動きを気にする必要がありません。
初心者の方にはリスクを抑えつつ、投資のタイミングに迷うことがない「つみたて投資枠」がおすすめです。
NISAのはじめ方
NISAをはじめる手順は以下の通りです。
どの金融機関でNISAをはじめるかを選びます。店舗型の証券会社やネット専業の証券会社、銀行でも可能です。取り扱い商品や積み立ての最低金額など金融機関ごとに違いがあるので比較して選びましょう。
口座開設には本人確認書類やマイナンバーが確認できる書類が必要になります。申し込みから1週間程度で口座開設されるのが一般的なようです。
口座が開設されたら、商品・つみたて金額・購入のタイミングを決めて、商品を購入しましょう。
会社員でも新NISAは利用できる?
新NISAは会社員でも活用できる税制優遇制度です。安定した収入のある会社員こそ、定期的に一定額を投資する「つみたて投資枠」は利用がしやすいでしょう。



節税の方法が少ない会社員にもうれしい制度だね!
まとめ
本記事では、新NISAの仕組みやメリット・デメリットについて解説しました。
2024年からスタートした新NISAにより、さらに使いやすくなりました。
「NISAが気になっていたけど難しそう」と感じていた方も、ぜひこの機会に「つみたて投資枠」からはじめてみてはいかがでしょうか。